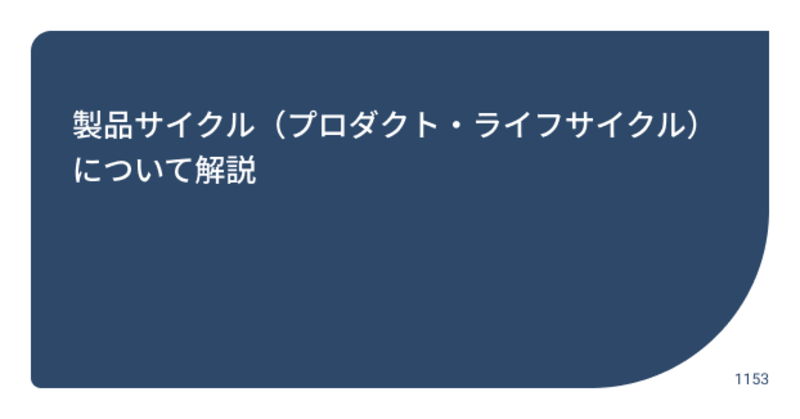 製品サイクルとは発売された製品が衰退するまでのプロセスのことです。プロセスはそれぞれ4つにわけられます。それをしっかりと捉えることで最適なマーケティングを行えるでしょう。
製品サイクルとは発売された製品が衰退するまでのプロセスのことです。プロセスはそれぞれ4つにわけられます。それをしっかりと捉えることで最適なマーケティングを行えるでしょう。
・工業製品・食品などで使用されている製品サイクル(プロダクト・ライフサイクル)の概要
・製品ライフサイクル理論とは?段階ごとに事例やマーケティング手法を解説
・製品ライフサイクル理論のメリットや具体的な戦略を解説
・製品ライフサイクル:衰退期における最適な販売戦略とは
・まとめ
工業製品・食品などで使用されている製品サイクル(プロダクト・ライフサイクル)の概要
製品サイクルは英語でプロダクトライフサイクルと呼ばれています。 1950年頃「マーケティング」という新しい学問が始まりましたが、その際ジョエル・ディーンが製品サイクル理論を提唱しました。
製品ライフサイクル理論とは?
製品サイクルは新しい工業製品や食品などが市場に出てから衰退するまでの流れを具体的に表した理論です。 製品サイクルには4~5つの段階にわけられ、それぞれの段階時では売上と利益が異なります。 そのため、現在の自社のサービスや製品がどの段階なのかをしっかりと捉え、把握することでコストの削減にもつながります。 製品サイクル理論を理解し、企業のマーケティング戦略に役立てましょう。
製品ライフサイクルの4つの段階
製品ライフサイクルは4~5つの段階に分かれています。
製品を市場に投入した最初の時期は「導入期」でまだ製品の認知度が低く売上利益は少ないです。 次に、製品が市場に認知され普及される段階「成長期」に突入します。成長期では市場も拡大するため売上利益も多くなります。
市場が拡大し競合他社から類似の製品が発売されると自社製品に新しさは感じませんが、認知度があるためシェアは安定する「成熟期」となります。 次の「飽和期」ですが、競合他社との競り合いで価格も低下し、また新規の購入需要が減る段階です(この飽和期がない場合は4段階となります)。
さらに、製品の需要が減少し、売上利益も低下した段階は「衰退期」となります。
短縮する製品の寿命
現在では経済が成熟し消費者の嗜好が多様化しています。そのため市場の様々な製品のライフサイクルが短縮化してきています。 1つの製品にも類似品が多く販売されていますので「物」が余っているのが現状です。
以前は製品サイクルの「成長期」「成熟期」が長くその間に多くの利益を得ることも可能でしたが、現在では自社商品がヒットしてもある程度市場に出回ってしまうと頭打ちになるでしょう。 少子高齢化社会や消費者ニーズが変化してきたなど、理由は様々ですが「製品サイクル」が短くなっていることもマーケティング戦略においては考慮する必要があります。
製品ライフサイクルの概念図
製品サイクルの概念は、1つの製品や商品を販売し、開始直後から販売を終了するまでのあいだを段階にわけた理論です。
製品サイクルを理解し取り入れることがマーケティング戦略には必須となります。 ひとつの製品をつくるコストは変わりませんが、生産量が多くなればなるほどコストは下がります。単純にいえば成長期に生産を拡大すると売上利益も上がるというわけです。
ただし、上記したように現代では製品サイクルが短縮化の傾向です。成長期や成熟期を見極めたマーケティングを行い、衰退期にはいると撤退する方針に変更するのも考慮しましょう。
製品ライフサイクル理論とは?段階ごとに事例やマーケティング手法を解説
製品サイクルとは段階にわかれています。それぞれの段階の特徴をとらえ、マーケティングを行う必要があります。 製品サイクルの段階に合わせたマーケティング手法と、各段階にある製品の例を挙げます。
製品ライフサイクルの導入期
製品サイクルのまず最初は「導入期」です。自社のサービスや商品を市場で販売開始した段階です。 製品は開発や改良のために設備などを導入し自社は費用もかかっていますが、消費者の認知度は低く、売上利益はあまり見込めないでしょう。 導入期は赤字になりがちですが、とにかく消費者への認知度を高めるようなマーケティングを行いましょう。
消費者は「よくわからないもの」を敬遠しますので、製品に関するマニアや業界にむけてサンプル提供などをおこない、まずは自社製品を知ってもらうことが大切です。 成功した事例では展示会や一般の消費者に向けて安全性をアピールした「自動運転機能付き自動車」があります。
製品ライフサイクルの成長期
製品が認知されると市場が拡大します。成長期では売上利益も増加するでしょう。 半面、競合他社から類似の製品が発売される時期でもあります。売上は見込めますが、競合他社製品に勝つためには、宣伝広告費やさらなる商品の改良といった費用も必要になります。
また、消費者のニーズを調査し、さらなる需要が見込まれるようであれば、すみやかに生産体制や販路などを整備しなければ供給が追いつかなくなってしまうので注意してください。 成功事例ではネットに接続できるテレビ「スマートテレビ」があげられます。
製品ライフサイクルの成熟期
自社製品の認知度が高まり市場が安定する「成熟期」では、新しさもなくなり他社との競争で価格を低く抑える必要も出てくるでしょう。 そのため、売上は安定していますが利率が悪くなる可能性が高いです。
利益を上げるためには、ターゲットを広げる努力が必要です。メディアへの露出や他社との差別化を行うのもよいでしょう。 成功事例では、現代では必須のスマートフォンが挙げられます。
製品ライフサイクルの飽和期
自社製品だけでなく競合他社の類似商品が出回り市場に浸透した状態が「飽和期」です。この状態になると新規購入者も増えることはないでしょう。そのためリピーターを確保することが大切です。 コストを抑えるため派手な宣伝は行わず、ユーザーの意見を調査しニーズに答えた製品改良といった戦略を実行しましょう。 成功事例では、現代では当たり前になった薄型テレビです。
製品ライフサイクルの衰退期
消費者ニーズが縮小すると利益をあげることはできません。製品サイクルの衰退期は多くの企業が撤退しています。 しかし「継続する」という戦略をとるのであれば、既存ユーザーへのサポートを徹底し、新しいコンセプトを打ち出す必要があるでしょう。 現在衰退期になっている製品は「DVDプレーヤー」や「ガラケー」があげられます。
製品ライフサイクル理論のメリットや具体的な戦略を解説
次に製品サイクルを知るメリットやそれぞれのマーケティング戦略を解説します。
製品ライフサイクルを知るメリット
製品サイクルを理解していると、各段階に沿った戦略をとることができます。自社の製品が今現在どの段階なのかを把握すると適切な対応ができ、利益をあげることが可能です。 また、導入期から衰退期まで、それぞれのタイミングでコストの計算もできるでしょう。
製品ライフサイクルに関わるイノベーター理論
製品サイクルに深く関わってくるのが「イノベーター理論」です。イノベーター理論とは、製品導入後、どのように、どのくらいの割合で普及していくのかを分析した理論です。 まず、導入期にはイノベーターと言われる新製品への許容度が高く、新しいもの好きな層がメインです。次に成長期ではアーリーアダプターと言われる流行に敏感な「オピニオンリーダー」的な存在の層が顧客になるでしょう。
成熟期になるとアーリーマジョリティと言われる、メリットとデメリット、周囲の評判などを参考にして製品を購入する層がターゲットです。 飽和機のメインとなるのはレイトマジョリティと言われる、新製品に抵抗を感じる層と、ラガードと言われる新製品は受け入れない、または購入までに時間がかかる層もユーザーとなります。
短期化する製品ライフサイクル
大量生産大量購入であった以前は製品サイクルも長かったのですが、現代では製品も多様化しサイクルが短期化しています。 様々なツールから情報を得られるため市場ニーズの変化やユーザーが飽きるのも早くなっています。そのためそれに合わせた迅速な対応が求められるでしょう。
製品ライフサイクル運用時の注意点
製品サイクルはすべての製品に当てはまるわけではありません。季節ごとの商品(蚊取り線香など)や生活必需品(冷蔵庫や洗濯機など家電製品)などは一般的な製品サイクルには関係ないため、判断基準にはなりません。 また、製品サイクルは一つの理論です。全てがその通りに運ぶわけではないことも頭に入れておく必要があります。
製品ライフサイクル:衰退期における最適な販売戦略とは
製品サイクルの衰退期には売上が減少するため利益をあげるのも難しいです。衰退期におけるマーケティング戦略を解説します。
製品ライフサイクル衰退期の特徴・課題
衰退期では販売数も減りますが価格も低下せざるを得ません。そのために市場から撤退する企業も多いです。 ただ撤退してしまうと既存ユーザーへのサポートや従業員の雇用問題といった課題がでてくるでしょう。
衰退期の最適な戦略とは
衰退期で撤退するとその製品は「失敗」と印象づけられます。そうならないためには、新しい製品へ以降したというイメージをつくることが大切です。また、コストがかかる製品は排除し、よりニッチな層をターゲットにするのも良いでしょう。 衰退期は悪いことばかりではありません。コンセプトを変更したり戦略の見直しをおこなったりして新しい市場へと乗り出すと、競合他社は撤退しているため市場を確保できる可能性もあります。
まとめ
製品サイクルを理解することで自社が各段階に沿ったマーケティング戦略を行えます。ただし市場のサイクルは時に予測できない動きをする可能性もあります。製品サイクル理論と現実の自社の売上や利益を同時に考慮することでリスクやコストを抑えることができるでしょう。