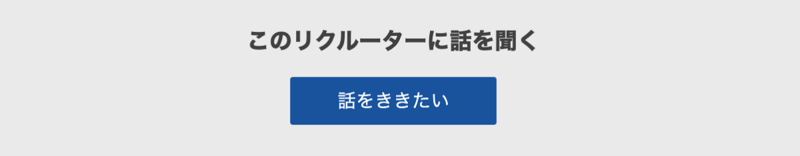知名度に惑わされるな。キャリアを切り開く人が持つ「ファーム選びの視点」とは
sponsored by KVC Partners

自らの市場価値を高められる舞台として、コンサルティングファームを目指す人は多い。しかし現実には、入社前に描いていた理想とのギャップを感じて転職を後悔するケースも少なくない。
IT・コンサル領域に特化した人材紹介エージェントKVC Partners(KVC)の大橋花織氏は「“それっぽい”横文字や大手の知名度で安直に判断する人が転職に失敗している」と指摘する。
真にキャリアを前進させるためのコンサルティングファーム選びには、どんな視点が必要なのか。KVCの支援先であるファーム、Xspear Consulting(クロスピア)の代表取締役社長早田政孝氏との対談で語り合ってもらった。2人の言葉は、これからコンサル領域を目指す人にも、またコンサルからコンサルへの転職を考えている人にとっても大きな指針となるはずだ。
※内容や肩書は2024年9月の記事公開当時のものです。
クロスピアとKVCは仕事に対する価値観を“共有”できている
――早田さんが2021年にクロスピアを立ち上げた理由を教えてください。
早田:端的に言えば、シンプレクスグループの成長のステージが変わったからです。2014年時点で約120億円だったグループ売上高は、2024年3月期には400億円を超え、10年で3倍超に成長を遂げました。2030年ごろまでには1000億円超えを目指しています。
会社そのものも変わりました。かつてのシンプレクスは金融×IT領域のスペシャリスト集団だとみられていましたが、昨今では事業会社の社運を懸けた挑戦を支援するプロジェクトや、中央省庁のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援も手掛けるようになりました。技術力を強みとするだけでなく、事業会社のシビアな判断や省庁間のハードな交渉にも私たちは積極的に関与する立場となったのです。
シンプレクスは1997年の創業以来、「テクノロジーファースト」を掲げて技術力を伸ばし続けてきました。しかしその裏返しでテクノロジーとの関わりが強くないキャリアの人たちからすると、少し近寄りにくい企業だったかもしれません。
だからこそ、システム開発フェーズよりもさらに上流で抽象度の高い経営アジェンダを取り扱い、先端技術を取り入れながら企業の変革を支援するコンサルティングファームとしてクロスピアを立ち上げ、従来のシンプレクスでは接点を持ちにくかった異なる才能を持った人たちを集めていくことにしました。
――KVCではクロスピアをはじめ、シンプレクスグループ全体で数多くの紹介実績を有していると聞きました。この秘訣 (ひけつ)はどこにあるのでしょうか。
大橋:私たちはIT・コンサル領域に強みを持つエージェントです。これらの領域ではビジネスモデルの差別化やスキルセットによる人材マッチングは難しく、企業のカラーをよく理解した上で、採用候補者の核となるモチベーションなどの定性面を深く見ながらマッチングを図る必要があります。
その点、クロスピアやシンプレクスの真面目でとがっているカラーは分かりやすく、個人的に強く共感できる部分もあります。「この方はクロスピアに向いているのではないか」と思われる採用候補者が見つかった際には、一気にギアを上げて高い熱量でクロスピアを紹介していますね。
――なぜそこまで熱くなれるのですか。
大橋:クロスピアやシンプレクスでは、誰と話しても仕事への価値観がぶれないんです。大前提として社員の皆さんは能力が高く、その優秀さを土台にして真面目に汗をかき、モチベーションがとても高い。エージェントのやる気に火を付けてくれる人たちなんですよね。
早田:当社の社員は、KVCに近い熱量の高さを持っていると思います。やるからにはその道でプロになると決め、約束したことは必ず遂行し、新たに挑む領域でも「ナンバーワンにならなければ意味がない」と考えています。このカルチャーに共感した人たちが集まっているからこそ、仕事に妥協がありません。

経験に加えてポテンシャルも重視して採用し、1000〜2000万円規模の年収を提示
――早田さんは中途採用の面接を行う際、採用候補者のどんな部分を見ていますか。
早田:学歴、職歴、これまでの実務経験以上に、その人のビジネスマインドや仕事に対する価値観を大切にしています。
もちろん、その人の能力を確認することも面接を行う目的の一つではあるのですが、「今後、何に挑戦をしたいか? 自分はどうなっていきたいか?」など、“未来志向”を持っている人かどうかを見ています。せっかく転職をしてクロスピアに入社するのであればハッピーになってほしいですからね。
――大橋さんはエージェントとして、この採用基準をどのように受け止めていますか。
大橋:人材を紹介する上で、とても分かりやすいスクリーニングの基準を示してもらっています。コンサルからコンサルへの転職だと、企業側は表層的なスキルセットの条件を求めることがほとんどです。ビジネスモデル上は、スキルのある人材を手っ取り早く現場に送って“稼ぐ”ことを優先するのも無理はないのかもしれません。
他のコンサルティングファームの場合、面接の質問で「こう答えれば通る」という型を持っているエージェントもあるくらい、スキルセットによる選考が一般化しています。コンサルティングファームはそれによって稼げる人材を手早く獲得でき、エージェントは紹介者数を増やして紹介フィーでもうけられるわけです。
でもクロスピアは本当に採用候補者の表面的なスキルセットを見ません。「これからどうしたいのか」に徹底的にフォーカスして選考を行っています。採用候補者にとっては、ごまかしが利かない会社でもあると感じます。
早田:大手コンサルティングファームは、「この経験があればどこのポジションに当てはまるだろう」という感覚で選考しているのかもしれませんね。また、タイトル(役職)が上位の人や高いスキルを持つ人に対しては、「どの業種、どの企業を開拓できそうか?」と具体的に聞くこともあると聞きます。
巨大なコンサルティングファームでは新しい組織をたくさんつくり、こうした人材のつながりを活用して仕事を増やしていきますが、「過去の人脈やつながりを棚卸しして終わり」になることも珍しくありません。
中途採用に、今伝えたようなアプローチがあることは理解できます。一方、立ち上がって間もない私たちのような会社では、個人のキャリアの強みや今後の可能性を重視するスタンスを大切にすることが、会社の風土をつくることにもつながると考えています。
大橋:この採用スタンスを貫きながら、クロスピアがとても高い年収を採用候補者に提示することにも驚かされています。未来志向で人柄を見て、ポテンシャルを重視した採用をしているのに、1000万円や2000万円という高い報酬水準のオファーが出ることもあります。
早田:グループ全体で見れば、早い人だと30代で年収4000万円を実現している人もいますね。
大橋:長期目線で人材と向き合っているからこそできることだと思います。

KVCがクロスピアと転職者のマッチングを精度高く実施できる理由
――大橋さんは採用候補者と向き合う際に、どんなことを大切にしていますか。
大橋:コンサル業界はビジネスモデルがどこも基本的に似ています。それ故、その人が持っている強みと転職先の企業の強みや特徴、課題を定性的な観点も含めて、高い精度でマッチングをさせることが非常に重要になります。コンサルタントは市場価値が高いといわれる職種の一つです。それだけにコンサルタントという仕事の本質的な意義を理解せずに入ってくる人が多いと感じています。
キャリアカウンセリングの場では、転職者が今まで経験してきたことや、自身の強み、現職に対する課題は何なのか、精緻なヒアリングを行います。
同時に、私たちは企業側の採用ニーズについても、定量、定性の面で把握しています。企業が提供できるキャリアパスや業務内容と、候補者の現在の個人が持っている知識や能力、将来なりたい姿などを確実に把握しているからこそ、両者を高い精度でマッチングできるのです。
――クロスピアを志望する人を例に取ると、どんな支援を行っているのでしょうか。
大橋:志向性は非常にいいのに、現状のままだと面接通過が厳しいと感じたときには、面接準備を徹底的に行っています。クロスピアの人事から連携される現場の細かい気付きとの評価と擦り合わせながら候補者と何度も電話で壁打ちを行いモチベーションの整理をして、面接の場でどのように伝えるべきか、アドバイスをします。
クロスピアの面接は本当に難関なんですよ。例えば、最初の面接で「戦略」という言葉を曖昧に使った採用候補者が、次の面接でも同じように不明瞭に戦略を語った場合、ほぼ間違いなく落とされるでしょう。クロスピアの人たちは同じ価値観を持っているので、面接官が変わってもごまかせません。
逆の側面で言えば、クロスピアの選考を受けることでコンサルタントとしての自分の価値観を見直し、バージョンアップにつなげている人も多いです。最初から価値観やモチベーションが明確になっていなくても大丈夫です。漠然とした状態から自信を持って語れる状態になるために、クロスピアの人事の皆さんも選考中にうまくサポートしてくれますから。
早田:先ほど言ったように、私たちは候補者の成長意欲や未来志向に基づくポテンシャルを引き出したいと考えています。選考過程ではそのためのコミュニケーションを重ねていきますし、人事メンバーはKVCと連携して採用候補者を深く理解できるように努めています。
また、私たちは「クロスピアを選んでもらうことが本人にとってハッピーではない」可能性がある方を、無理に口説いて入社してもらうことはありません。一時的に見せかけの採用人数を増やしても意味がないからです。クロスピアで働くことは自分の人生にどのような意義があるのかを、ご自身で徹底的に考えてほしいと思っています。
社名には意味がない。「踊らされないファーム選び」に必要な視点とは
――コンサルからコンサルへ、あるいは異業種からコンサルへの転職を考えている人へアドバイスをください。コンサルティングファームを選ぶ際には、どんな軸を持つべきでしょうか。
早田:コンサルティングファームは大きく三つに分類できます。大手総合コンサルティングファームと新興コンサルティングファーム、そして大手親会社からスピンアウトしたコンサルティングファームです。これらの特徴を理解し、自らが目指すキャリア像に照らし合わせて考えるべきだと思います。
大手は大規模なプロジェクトを得意としています。ただ組織内には下は22歳から上は65歳くらいまで、数千人から数万人規模の強固なピラミッドがあり、その中で評価を得ていくことを余儀なくされます。人事戦略の中で“引き上げる”対象になった人に多くの報酬が分配される世界です。入社時に年収2000万円のオファーが出ても、社内評価次第では将来的なアップサイドを大きく見込めないことがあるかもしれません。
対して新興コンサルティングファームでは個人の活躍によって報酬が大きく跳ね上がることも期待できそうです。新興コンサルティングファームのコンサルタントには、顧客の社員の代替を担う側面があると感じています。顧客の事業会社で人材を確保できない場合に外部エキスパートへのニーズが発生します。ここに対応しているのが、新興コンサルティングファームなので、どのような仕事を任されるのかは慎重に見極めるべきでしょう。
最後に、スピンアウトしたコンサルティングファームは、大手の看板を使えることが強みです。一方、数万人規模の親会社の下で数百人の子会社を運営しているような事業形態なので、グループ内でリスペクトを得られているかどうかが仕事のしやすさにつながってくるため、注視すべきではないでしょうか。
クロスピアもスピンアウトしたコンサルティングファームだとみなされる場合がありますが、私たちはホールディングス体制でシンプレクスとクロスピアが対等に並び、コンサル領域ではクロスピアが強いイニシアチブを発揮しています。こうした組織の成り立ちを見ることもコンサルティングファームを選ぶ上でのヒントになると思います。
大橋:エージェントの立場としては、社名で選ぶことは本当に意味がないと伝えたいですね。
コンサルの世界ではそれっぽい横文字に踊らされることが多く、「大手の看板があるから」と安心してしまうこともあるでしょう。しかし、どんなにブランド力がある大手でも、中で行われているのは社内政治ばかりかもしれません。安直に判断すると入社後に大きなギャップを感じる恐れもあります。
何のために、誰と働き、どんな価値を社会へ提供したいのか。コンサルタントとしてのモチベーションを整理し、心の底から納得感を持って転職先を選んでほしいと考えています。ベストな決断ができるよう、私たちも妥協することなく一緒に考え抜きます。
また、シンプレクス・クロスピアについてKVCは熟知しています。他では扱っていない情報も持っていますので、気になる人は相談してください。