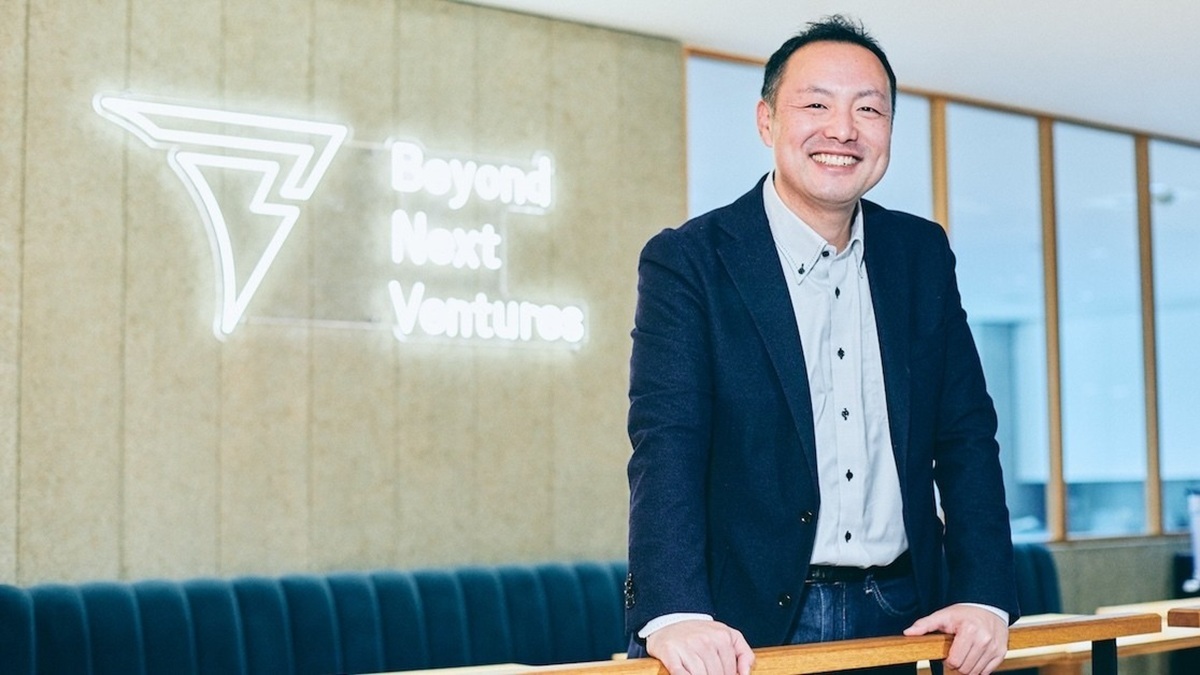「研究者×海外志向経営者」で世界に挑め。VCが仕掛ける、ディープテック起業家育成の新構想
sponsored by Beyond Next Ventures

「大きなインパクトを残したい」「技術を軸に世界市場で勝負できるビジネスを創りたい」――。そんな野心を抱きながらも、踏み出せずにいる人に知ってほしいのが、世界市場を見据えた技術シーズの事業化に挑む創業経営者を育成するプログラム「PEAK TRIAL」だ。
このプログラムはディープテック領域で国内トップクラスの投資実績を誇るベンチャーキャピタル(VC)、Beyond Next Venturesが提供する新たな起業の選択肢。現職を継続しながら最大12カ月の準備期間を確保でき、研究者とのマッチングから創業までを同社が徹底支援する。3号ファンドでは1社あたり最大累積20億円の投資枠を設定し、グローバル展開を見据えた長期的な成長をサポートする体制も整備されている。
今回は、プログラムを運営するBeyond Next Venturesの執行役員、鷺山昌多氏にインタビューを実施。日本のディープテックが大きな転換期を迎えている今、鷺山氏は市場の可能性をどう見ているのだろうか。PEAK TRIALが目指す世界戦略について詳しく話を聞いた。
※内容や肩書は2025年2月の記事公開当時のものです。
現職を続けながら起業家を目指せる、新プログラム「PEAK TRIAL」
――PEAK TRIALはどのようなものなのでしょう。
近年、スタートアップ創出の手法として「EIR(Entrepreneur In Residence:客員起業家)」の活用が進んでいます。EIRでは、VCや事業会社が起業家や社内起業家を創出するために、起業家候補を外部から雇い入れます。
一般的に、EIR活動を通じて「創業」を実現するためには、EIRとして多くの時間を確保し、シーズ探索活動に投下する必要があります。われわれはそのハードルを少し下げて裾野を広げることを目指し、起業家志望者が即現職を辞める必要がなく、必死に事業シーズを探す活動を軽減し、創業準備が実現できる「被スカウト型」のEIRを作りました。それが、ディープテック領域で国内有数の研究者と共にスタートアップの創業に挑むプログラム「PEAK TRIAL」です。これは2017年から当社が積み重ねてきた、シーズマッチング型創業プログラム「INNOVATION LEADERS PROGRAM(ILP)」のさらなる高みを目指した発展形であり、グローバル展開を見据えた技術シーズの事業化を目的としています。
――Beyond Next Venturesはディープテック領域に特化したVCですが、そもそもディープテックとはどのような領域を指すのでしょうか。
一般的に、大学や研究機関での長期的な研究から生まれる高度な科学技術やエンジニアリングを基に、社会課題の解決や革新的なプロダクト・サービスを生み出す領域を指します。 市場に普及するまでに時間や資金がかかる一方で、実現されると大きな社会的インパクトをもたらす可能性が高いのが特徴です。
当社は2024年で創業10年を迎えましたが、この10年で日本のディープテックスタートアップの環境は大きく変わりました。大学発ベンチャーの総数は、ここ6〜7年で倍以上に激増し、各大学がスタートアップの数を競い合う世界になってきています。
もちろんスタートアップは創業しただけでは意味がなく、社会実装を通じた社会課題の解決やビジネスとしての成功も求められます。ただディープテック領域は、成果が出るまでに長い時間を要するため、日々の生活の中で、体感できる形でディープテックスタートアップの成果を目にする機会が頻繁にあるわけではありません。
一方で、ディープテック市場は年々盛り上がっています。既に国内スタートアップの資金調達金額ランキングを見てみると、大型調達の花形はディープテック領域の企業です。以前はSaaS等の企業が多くを占めていましたが、時代が移り変わりつつあります。

――なぜ日本のスタートアップは、ソフトウエアからディープテックへと移り変わっているのでしょう。
グローバル展開の容易さにおいて、根本的な違いがあると考えています。ソフトウエアは「UX」が絡むサービスのため、カルチャーや言語の壁を超えなければなりません。そのため、市場がおのずと日本国内に狭まってしまいます。
一方、ディープテックには基本的に言語の壁がありません。医療や素材研究も含めその成果は人類共通で活用でき、対象市場が全世界に広がります。加えて、ディープテックは「研究の積み上げ」がものをいう領域です。その点、日本の研究投資額やPCT国際特許出願数はいまだ世界上位の一角であり、歴史的な蓄積もあります。
当社がPEAK TRIALを通じて成し遂げたいことは、日本が積み上げてきた知恵を活用し、世界に挑むスタートアップの創業を加速することです。日本はディープテックで世界をけん引するポテンシャルを持っているものの、世界規模での大きな成果を出している企業は多くありません。その殻を破るために、独自の変形型EIRを作ったのです。
最大累積投資金額は20億円。全事業フェーズを支援するファンドを組成
――VCとして投資や創業までの伴走を担っているそうですが、具体的にはどんなことに取り組んでいるのですか。
当社が果たす役割は少しずつ変わってきています。10年前は、「サイエンスを理解する創業初期からのリード投資家」が限られており、その役割を担うべく1号ファンドがスタートしました。ディープテック領域の投資においては「その研究の真価」を見極める必要があるのですが、投資家からすると投資判断がしづらい領域なんです。そこを理系出身のキャピタリストたちが、研究者と共に事業計画を議論し、同時にVCとして創業初期から伴走してきました。
10年がたち、現在はサイエンスを理解する投資家が増え、創業初期フェーズのスタートアップへの投資額も増加しています。とはいえ、ディープテックは成果が出るまでに時間も資金も要します。当社の3号ファンドは、1社に対する最大累積投資金額を20億円に引き上げ、運用期間も最長14年に設定し、プレシードからより大きな資金が必要なグロースフェーズ以降も含め継続的にファイナンスをけん引する体制を整えました。

――資金が欠かせない一方、「資金さえあればスタートアップは立ち上がる」わけでもないと思いました。
確かに、資金があったとして、企業価値1000億円を目指すビジネスが作れるかというと、決して容易ではありません。20年前から言われていますが、ディープテックスタートアップの最大の課題は、その事業を実現する「優れた経営者が極めて不足していること」です。
研究の社会実装を志向する研究者であっても、自身は研究を担うことを志望し、経営のかじ取りはその道のプロに委ねたいという人は多いです。実際に、サイエンス側とビジネス側でお互いを支え合うco-founder体制のスタートアップは非常に多いです。また、「経営者がいないから創業ができない」という声もよく聞きます。それを解決するために2017年から起業未経験のビジネスパーソンを中心とした研究者とのマッチング型創業プログラムをローンチし、累計約550人がプログラムに参加しました。
目標はグローバル展開。初めからホームランを狙っていく
――PEAK TRIALのプログラム内容を教えてください。
起業志望者が当プログラムに応募して審査に合格すると、共同創業候補として登録され、当社が投資を目指して創業支援を行う技術シーズの共同創業者として、スカウトを受けられる仕組みです。マッチング後は、当社のベンチャーキャピタリストの支援の下で現職を継続しながら最大12カ月の創業準備を進めます。
当社は本プログラムを通じて、創業の実現と共に投資実行を目指しています。VCの投資実行確度の高い厳選されたシーズを持つ研究者から誘いを受ける機会は、VCとの直接の信頼関係なしには得難い機会であり、登録する価値はあると思っています。
本プログラムは、共同創業のスカウトを待つだけのプログラムではありません。審査通過者は、共同創業の実態を知る機会や、キャピタリストとの交流の場など、創業に必要な知見を得られる交流会や勉強会に参加することができます。さらに、今後は創業を目指す研究者との大規模な交流イベントも予定しており、研究者との共同創業についてステップを踏んで理解を深める機会もあります。つまり「起業に興味はあるものの、人脈や知見がない」という人が、段階を踏んで創業に至れるプログラムになっているんです。
研究者とマッチングしてから創業準備に入るまでの期間は最大12カ月確保されており、「この研究者と一緒にやっていけるか」「このビジネスモデルの市場における評価はどうか」などをじっくり検証した上で創業できるのもポイントです。現職との兼業や副業が可能で、創業準備に入ってからは報酬も支給されます。これまで数多くの共同創業を実現してきた当社だからこそ提供できるプログラムではないか、という自負があります。
――PEAK TRIALの最終目的は何なのでしょう。
2017年に前身のプログラム(ILP)を作った当初は、共同創業者を見つけてスタートアップを創業してもらうことが目的でしたが、今は「世界で勝ち抜けるグローバルスタートアップの創出」という、より視座の高い目的を見据えてプログラムを運営しています。
例えば、米国市場に挑むのであれば、米国のスタートアップ、そして英語圏も含めた米国を目指す全てのスタートアップがライバルです。創業時からその市場で勝ち抜くことを目指して体制を構築していくのが当然で、「とりあえず日本市場からスタートし、機会があれば海外展開しよう」で勝てるほど容易な道のりとは思えません。
大きな野心を抱く人、「人生の10年を懸ける挑戦なら、世界に挑むのが当たり前だ」と考える “ダイヤモンドの原石”のような人と出会うために、PEAK TRIALを始めました。

――過去に共同創業したスタートアップの事例を教えてください。
当社のプログラムを通じて生まれた共同創業を果たした人は数十を超え、国内最大規模を誇ります。例えば、植物由来化学物質の生産に取り組むファーメランタの最高経営責任者(CEO)である柊崎庄吾氏は、当社プログラムを通じて大腸菌での植物二次代謝産物の生産において世界をリードする研究者である南博道氏、中川明氏(石川県立大学所属)と出会い、約1年で共同創業を果たしました。
柊崎氏は文系出身で研究者ではありませんでしたが、欧州で研究が進んでいるバイオマテリアル領域に興味を持ち、共同創業シーズを探すために当社の門をたたいてくれました。
また、代理親魚技法(*)による魚の新品種を生み出す、さかなドリームの代表取締役CEO細谷俊一郎氏、共同創業者である取締役CMOの石崎勇歩氏も、当社キャピタリストとの創業を目指したEIRの取り組みを経て、東京海洋大学の吉崎悟朗氏、森田哲朗氏と共同創業を実現しています。
*魚(ドナー)の精子や卵のもととなる生殖幹細胞を、別の魚(代理親)に移植し、代理親が成魚になった際に“ドナー由来の魚”を産ませる技術
「挑戦心」と「行動力」を持つ全てに、門は開かれている
――PEAK TRIALで創業者候補を募るにあたって、どのような資質を求めますか。
一つ目は、研究やサイエンスへのリスペクトを持てること。研究が持つ「社会を変える底力」を信じられることや研究者の情熱に共感できることはコミュニケーション上重要です。二つ目は、社会に影響を与える大きな挑戦にこそ価値を感じる人であること。その大きなイノベーションを起こすための道筋として、ディープテックを選んでくれるとうれしいですね。三つ目は、柔軟さと行動力です。自身の専門性を磨くことのみで世界トップの戦いを勝ち抜くことは容易ではありません。未知の挑戦の中で自らも柔軟に変化を取り入れ、また最適な仲間が集い、さらに高みの戦いを目指すことでゴールは近づいていくのではないでしょうか。
――過去のプログラム参加者には、どのような経歴の人が多いですか。
人柄としては、本質的に自己信頼感が高く、自身の価値観に沿った意思決定ができる人が多いです。自らの価値に沿って生きている経営者が親族にいる人や、起業家の近くで働いたことがある人もいます。はたまた商社やコンサルティングファームに入社しつつも、より挑戦的な世界を目指して若くして外へ飛び出したいと思ってプログラムに参加する人も多くいます。もちろん業種や職種で判断することは決してありません。「真摯に起業を通じて世界に挑もうという意欲」と、「小さな失敗を乗り越えて最後までやりきる実行力」がある人であれば、既に挑戦のエントランスパスは持っていると思ってください。
起業の経験や、ディープテックやサイエンスに関する知識も必須ではありません。足りない知識を補ってくれる研究者や開発者と手を組めばいい話ですから。たとえ実際の創業までたどり着かなくとも、「自分は創業に向けて動いた」と胸を張って言える一歩を、私たちは用意しています。