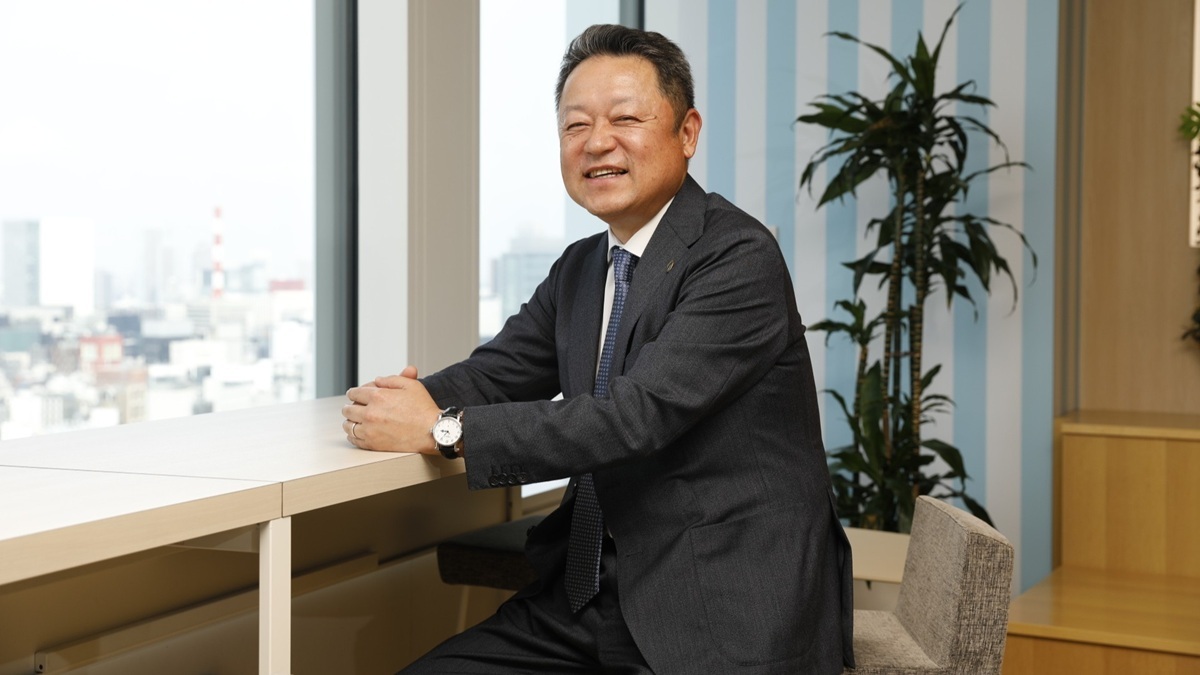世界34万人のエキスパートと共に学び、挑戦する。グローバル人材として成長し、望む未来を手に入れるために
sponsored by キャップジェミニ

キャップジェミニは2025年、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(以下、BTC)を統合し、公共分野やクラウド領域でのプレゼンスを一気に拡大した。現在、同社で公共・サービス産業事業部を率いるのが、元BTC代表の杉山健氏である。欧州発のキャップジェミニの文化とグローバル34万人のネットワークを活用することで、かつて米系コンサルティングファーム在籍時に感じた「外資系コンサルの限界」を打破し、日本市場に新たな価値を提供している。今回は、統合の舞台裏から今後のビジョン、そして求める人材像まで語ってもらった。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。
“外資系の限界”も“独立系の壁”も超えて。
グローバルの最新知見をスピーディーに取り込むための決断
――これまでのキャリアと、BTCの代表(当時)としてキャップジェミニにジョインした経緯について教えてください。
杉山:まず、私のキャリアは1993年に外資系コンサルティングファームへ新卒入社したところから始まります。約20年間、官公庁や医療機関を中心にITコンサルティングに従事し、非常に有意義な経験を積むことができました。自分自身を成長させてもらったと感謝しています。
しかし、時間の経過とともに自身のポジションが上がっていく中で、「外資系コンサルの限界」を感じる場面が出てきました。例えば、注力するサービスやデリバリーの形態にグローバルの考え方が強く反映されることで、日本のクライアントの課題に十分に対応できなくなるといったことです。
もっと自分たちの判断でスピード感を持って最適なサービスを提供したい。そんな思いを抱いていた時、元部下が立ち上げたBTCから声を掛けてもらい、参画を決めました。BTCではコンサルタントとエンジニアの垣根を取り払い、課題のヒアリングから解決までを一気通貫で担うスタイルを実現でき、とても充実した日々でした。
順調に成長し上場準備を進めていましたが、その最中に世界的な経済環境の変化が起こり、上場計画はいったんストップすることに決めました。ただ、そもそも上場を目指した動機は、規模を拡大し「グローバルの最新知見をスピーディーに取り込む」ことです。その目的は、必ずしも上場にこだわらなくても実現できると気付き、最終的に外資系ファームであるキャップジェミニとの統合の道を選択したのです。
――なるほど。外資系ファームの中でもキャップジェミニを選んだ理由は何だったのでしょうか。
杉山:条件面もさることながら、キャップジェミニの環境やカルチャーが特に魅力でしたね。米系コンサルティングファームとは本質的に異なる特徴を持つ欧州発のキャップジェミニと共に、新しい市場を切り開くことに新鮮さと意義を見いだしました。幹部陣と議論を重ねる中で、迅速に意思決定をして現在に至ります。
――実際に統合した後は、想像していた環境と比べてどうでしたか。
杉山:統合完了からまだ1年に満たない段階ですが、キャップジェミニは想像以上に「ピュアグローバル企業」だと感じています。外資系出身の私でも驚いたのは、多国籍のメンバーと日常的に協働する機会がとても多いことです。官公庁案件のように制約がある場合を除き、基本的に世界各地の人材とチームを組み、グローバルな意思決定プロセスの中で最適なサービスを提供しています。
また、知識や事例の共有も圧倒的にスムーズです。例えば欧州の最新事例を知りたいと依頼すれば、すぐに現地のメンバーがオンライン説明会を開催してくれます。前職では海外視察が必須だった情報が、キャップジェミニでは日常的に共有されるのです。これは当社ならではの大きな価値ですね。もちろん個々人も努力してキャッチアップする必要がありますし、英語力も含めて決して楽ではありませんが、その分、得られる成長機会は計り知れません。
――キャップジェミニには、以前感じていた「外資系コンサルの限界」はないのでしょうか。
杉山:欧州系ファームであること、そしてコミュニケーション量の圧倒的な多さが、非常に大きな違いを生み出しています。もちろん外資系ファームである以上、サービスやデリバリー形態の方向性はグローバルから提示されます。ただしキャップジェミニでは、「グローバルの方向性は理解できるが、自分のクライアントには合わないのではないか」「クライアントにとって最適な方策が、他にもあるのではないか」といった議論が交わされるのが当たり前です。日本オフィスのインド人メンバーから、「グローバルではそうかもしれないが、日本市場には当てはまらない」といった声が上がることもあります。
私が求めていた「現場の知見を基に、クライアントに最適な解決策を提案するスタイル」が、自然と根付いているのです。これは私にとって、大きな可能性を感じられる体験でした。グローバルコラボレーションと、各拠点の裁量が自然にかみ合っているのは、ヨーロッパ企業ならではの特徴だと思います。結果として「グローバルに学びつつ、自分の判断で日本の顧客に最適な解を提供する」という理想的な環境が整っています。
個の専門性とグローバル知見を融合し、真の課題解決に挑む
――グローバルの知見以外にも統合によって得られたメリットがあれば聞かせてください。
杉山:まず大きく広がったのは、官公庁領域とクラウド関連の案件です。BTC時代に築いた中央省庁とのリレーションに、キャップジェミニのグローバルアセットが加わり、これまでにない価値を提供できるようになりました。例えばヨーロッパにおける各国省庁の動向を隔週の共有会でインプットし、それを日本の官公庁向けプロジェクトに生かすといった形です。クライアントからも「ヨーロッパの事例や知見をこれだけ持ってきてくれる会社は初めてだ」と高く評価されています。
また、統合完了のタイミングで組織を、従来の「ケイパビリティユニット」から、各業界のエキスパートを結集した「マーケットユニット(以下、MU)」という体制に刷新しました。金融(MU1)、製造(MU2)、公共・サービス(MU3)の構成で、業界ごとに責任を持つ仕組みになっています。
私はこの中でMU3をリードする役割で、官公庁や小売り・流通のクライアントに向き合っています。官公庁は「固くて動きが遅い」というイメージを持たれがちですが、デジタル庁の号令もあり、昨今、スピード感を持って大きく変わろうとしている分野です。最先端技術を駆使し、日本の未来や国民サービスの向上に貢献したいという人には、非常にチャレンジングで意義あるフィールドだと感じています。
――これからさらに強化したい領域や、成し遂げたいことはありますか。
杉山:今後さらに注力したいのは、「クライアントセントリックな取り組み」です。従来はどちらかというと「自分たちの専門領域を生かして課題解決できる顧客を探す」動き方だったのに対し、「顧客や産業が抱える根本的課題に向き合い、その解決方法を探っていく」というイメージです。
つまり「顧客の課題ベースで動く」ということですが、難しいのは課題を特定した後です。必ずしも自分の専門性を生かせる課題とは限らないので、解決するために最適なチームを組む必要があります。自分だけ、日本人だけで完結させるのではなく、「世界中の人材と協働しながら柔軟に課題解決に取り組む姿勢」が欠かせません。
――ということは、個人個人が独自の強みを持つことと、グローバルチームと協働する力の両面が求められるわけですね。
杉山:その通りです。一人一人が専門的な強みを持ちつつ、同時に「オーケストレーション力」を磨くことが求められます。キャップジェミニでは、SAPやクラウド、コンサルティングなどのケイパビリティラインが定義されており、入社時に各自が専門領域を選択します。しかしその枠にとどまるのではなく、クライアントの課題に応じて自ら領域を広げていく姿勢が重要ですね。
個人の専門性を極めながら、多国籍の仲間と共に成果を作り出す経験は、他では得られない成長機会になると確信しています。
グローバル×コラボレーション。キャップジェミニで得られる比類なき成長機会とは
――現在のキャップジェミニが求める人材について教えてください。
杉山:MU3では、「小売り・流通」と「官公庁」という二つの大きな領域をカバーしています。「小売り・流通」では、やはり業界知識や、SAPやクラウド関連など当社が得意とする領域のスキルを持つ人が望ましいですね。
一方で「官公庁」は少し特殊で、そもそも直接的な経験者はあまりいないでしょう。ですから、必ずしも過去の実務経験は必須ではなく、官公庁向けのコンサルやシステム開発に関心があり、国民サービスや社会の仕組みをより良くしていきたいという意欲を持つ人であれば歓迎します。
――未経験で入社した場合、どういうステップで成長していくことになるのでしょうか。
杉山:未経験者に求めたいのは「まずはシステムに触れてみること」です。コンサルタントであってもシステムをある程度理解し、動かせることが必要だと考えています。最初の一歩は独学でもいいので、プログラミング言語やクラウドサービスなどの基本を自分で学んでみてほしい。AIの進化によって以前よりも学習のハードルは下がっていますし、週末講座などでも短期間で基礎を身に付けられる環境が整っています。
そうした自発的な学びを経て入社してもらえれば、あとはプロジェクトの現場で実践を重ねながら、ロジカルシンキングや課題発見力といったコンサルタントとしての基礎を確実に養っていくことができるはずです。
――そういった人材がキャップジェミニに入社するメリットはどんなところだと思いますか。
杉山:最大の魅力は「ピュアグローバル企業」であることです。日本市場は少子高齢化や人口減少の影響もあり、国内だけでビジネスを展開していては持続的な成長は難しくなります。そうした中、キャップジェミニには、インド、ヨーロッパ、アメリカなど世界中の仲間と日常的に仕事をする環境があります。単なる英語のやりとりにとどまらず、各国の文化や考え方に触れながら一緒に成果を出していく。この経験はAI翻訳やツールでは絶対に置き換えられない、リアルなスキルに直結すると思います。
さらに特筆すべきは「グローバル×コラボレーション」の文化です。新入社員であっても、各国のエキスパートに問い合わせるとすぐに詳細な情報が返ってきて、必要であればオンライン会議を設定してくれます。34万人規模の大企業でありながら、ここまでオープンにナレッジが共有されるのは非常に珍しいことです。
この「コラボレーションのしやすさ」と「多国籍環境での協働」は、キャップジェミニでキャリアを積む最大のメリットだと考えています。国内にいながら世界を舞台に学び、成長し、成果を出せる場があるというのは、他社ではなかなか得られない経験でしょう。
――本当に素晴らしい環境ですね。最後に、転職を検討中の皆さんにメッセージをお願いします。
杉山:本気で転職を考えているなら、ぜひ「今すぐ」動き出してほしいと思います。変化のある場所にしか成長はなく、情報収集だけで数カ月が過ぎてしまう時間は非常にもったいない。特にコンサル・IT業界はスピード感が速く、半年迷うだけで数年分の経験を逃すことになりかねません。
キャップジェミニはグローバルに開かれたフィールドであり、挑戦すれば必ずそれに応えてくれる環境があります。日本の未来に不安を感じている人こそ、キャップジェミニで、世界とつながりながら社会に貢献するキャリアを築いてほしい。心からそう願っています。