シンクタンクとコンサルの違いとは。特徴とビジネスモデルも紹介
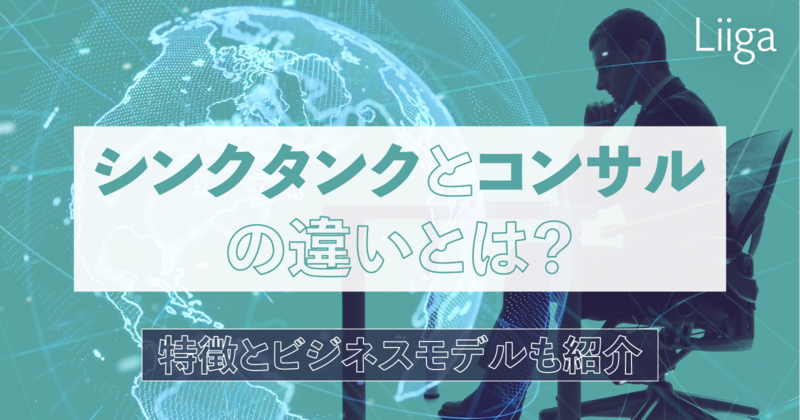
コンサルタントへ転職を考えている人で「シンクタンク」というワードに遭遇した方もいると思います。ここではコンサルとシンクタンクの違いについてご紹介します。 「コンサル・シンクタンク」という分類でまとめられたり、「シンクタンク系コンサルファーム」という企業分野も目にしますが、この2つの言葉にどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの転職に必要となるスキルやビジネスモデルの違いについても解説しますので参考にしてみてください。
シンクタンクとは?

コンサルタントは「Consult=相談」という言葉からも分かるようにクライアント企業の課題を見つけ、解決策を提案・実行支援し、営利を得る仕事となりますが、「シンクタンク」とはどのような定義があるのでしょうか。まず、コンサルタントとシンクタンクの定義の違いについてご紹介します。
シンクタンクの起源
シンクタンクの起源は19世紀後半にイギリスで創設された「フェビアン協会」や、20世紀初期にアメリカで創設された「ルッキングス研究所」とされています。社会問題や経済問題について調査・研究をおこない、政府に対して政策提言することを目的としています。
シンクタンクの仕事内容とは?
シンクタンクの仕事は大きく2つに分かれており、1つはシンクタンクのメインビジネスと言える「中央省庁の調査案件」をおこなう仕事で、もう1つはコンサルと同じような民間企業を対象とした「総合系コンサルティング」です。後者の総合系コンサルティングについてはコンサルファームと仕事内容は変わりません。これによりシンクタンクとコンサルをまとめて考えられることになるのです。
「中央省庁の調査案件」の仕事とは、省庁がおこなう政策立案に向けた各種調査を委託されるものです。これらの調査は、厚労省の社会福祉、経産省の補助金といった毎年ブラッシュアップが必要となる政策についての情報収集や、諸外国の取り組み事例の調査、国内企業へのヒアリングなどがおこなわれます。
シンクタンク系コンサルティングファームとは
1790年頃のシンクタンク発足当初は民間企業をクライアントとしたところが多かったのですが、石油危機やバブルの崩壊などの影響でシンクタンク業務が低迷し、公官庁への依存が強まりました。 経済状況の外部環境に左右される状況の問題解決に向け、経営を安定化させる狙いからリサーチ力を活かしたコンサルティング業務に力を入れるシンクタンクが生まれ、シンクタンクからコンサルへ業務の中心を変革した企業をシンクタンク系コンサルティングファームと呼ぶようになりました。
日本の大手シンクタンク
日本にあるシンクタンクはメインで扱う分野ごとに「政府系」・「金融系」・「証券会社系」・「企業系」など、政府や金融機関、大手企業などの母体となる組織によって分けられています。
- 経済社会総合研究所(内閣府)
- 経済産業研究所(経済産業省)
- 日本国際問題研究所(外務省)
- 日本銀行金融研究所(日本銀行)
- 日本経済研究所(日本政策投資銀行)
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(三菱UFJフィナンシャルグループ)
- 日本総合研究所(三井住友フィナンシャルグループ)
- 野村総合研究所(野村グループ)
- 大和総研(大和証券グループ)
- 三菱総合研究所(三菱グループ)
- NTTデータ経営研究所(NTTグループ)
この他にも民間企業や地方銀行でもシンクタンクを設けているところが多数あります。
シンクタンクとコンサルの違い
🔐この先は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。