R&Dとはどんな意味?企業が取り組む理由、大企業の事例、関連する部署・求人
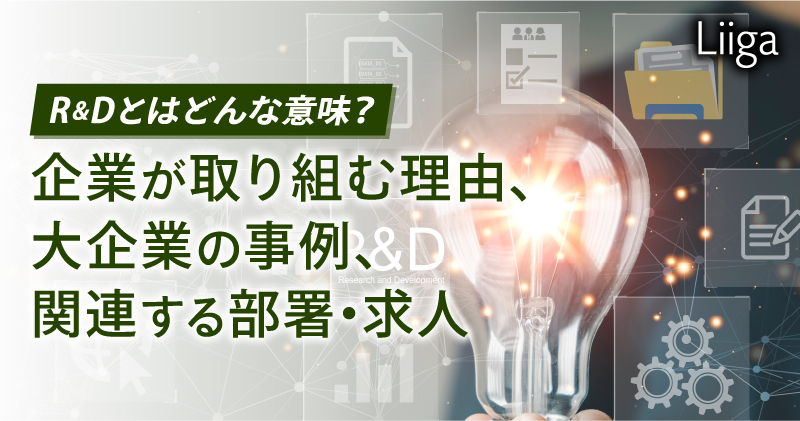
研究開発を意味するR&D。その具体的な内容、企業が取り組む意味を、トヨタや富士フイルムの事例を見ながら確認しましょう。R&Dに関わりたい人のための求人情報も紹介します。
R&Dとは研究開発のこと
R&Dとは「Research(研究)&Development(開発)」の略で、日本語では研究開発と呼ばれます。
企業にとっては投資の一つなので、「どんな分野の研究開発でも良い」という訳ではありません。新規事業の創出や既存事業の改善といった利益に繋がる成果を期待されています。そのため自社の事業に関わる分野、既存の技術が転用できる分野でR&Dを行うのが一般的です。
R&Dを通じて新技術や新製品を生み出すことができれば、他社との差別化に繋がります。また特許を取得できれば、特許使用料で利益を生み出すことも夢ではありません。

大きく3種類に分けられる
R&Dは、フェーズや目的によって以下の3種類に分けられます。
基礎研究
基礎研究とは理論的あるいは実験的な研究で、新たな科学的事実を発見・立証することをゴールにしています。利益に直接結びつくケースはほとんどありませんが、大きな社会変革の礎になることもある研究です。
企業と大学が共同で研究する「産学連携」の対象になりやすい研究でもあります。
応用研究
基礎研究の発見をベースに、具体的な実用化の可能性を探るのが応用研究です。基礎研究を利益に繋げる研究といえるでしょう。
また既存の技術について「他の分野で活用できないか」など新たな実用化の検討をするのも応用研究に含まれます。
開発研究
開発研究とは、基礎研究や応用研究の結果に基づき、新たなサービスや商品を開発するための研究です。新たな技術だけでなく、自社が使える既存技術や市場のニーズも踏まえながら、開発を進めていきます。
R&Dの最終フェーズであり、利益を生む商品やサービスを生み出すことが求められています。
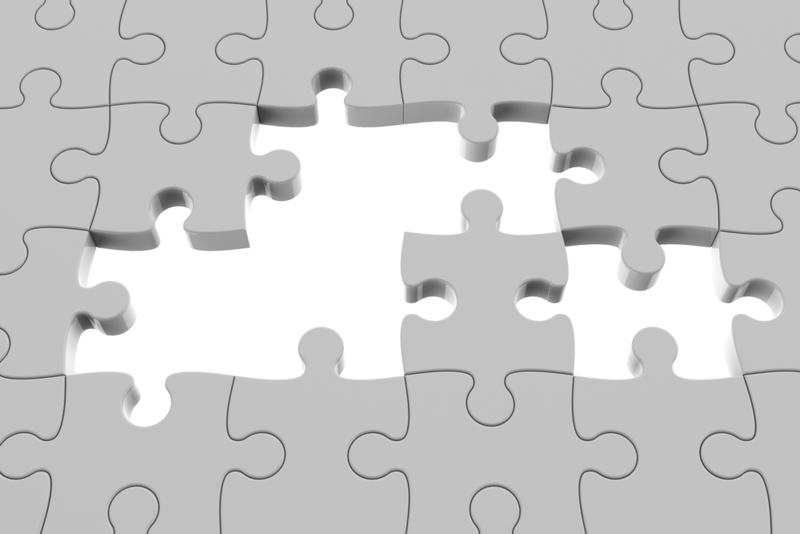
【おすすめ関連記事】
Q&A R&Dに関わるのは理系の人だけ?文系には無理??
「研究開発」という言葉から、「理系でないと携わることができない」と思われがちなR&D。確かに、基礎研究の仕事は「関連分野での修士号や研究実績があること」を求められることが多いです。そのため文系を含め、関連分野で実績のない人が、基礎研究を仕事にするのはハードルが高いでしょう。
しかし、開発研究などの分野では、社会や市場のニーズを踏まえることが求められるため、事業アイデアやプランが求められることも多く、マーケティング関連の担当者が参画する機会もあります。
特に最近では、技術などを起点に商品を作る「プロダクトアウト」ではなく、顧客ニーズから商品を作る「マーケットイン」の重要性が説かれています。そのためR&Dにおいても、社会や市場のニーズを捉えることができる人材の重要性は高まっていくでしょう。
R&Dの意義
R&Dにはコストもかかりますし、必ず新商品に繋がるとは限りません。それにも関わらず企業がR&Dに取り組むのは、以下のようなメリットがあるからです。
成功した時のメリット
- 新たな技術資産を手に入れられる
- 他社が真似できない新商品・サービスの開発に繋がる
- 商品・サービスの開発や改善スピードが上がる
R&Dに成功し、新たな技術資産を得ることができれば、様々なビジネスに展開できる可能性があります。またその技術を活かせば、他社に真似できない独自の新商品やサービスに繋げることもできます。
またR&Dに取り組む体制を確立できれば、片手間で商品開発や改善に取り組むのに比べ、開発スピードを上げることができます。先に技術や商品を開発できれば、特許を取得したり市場を確保したりと、ビジネスにおいては大きなアドバンテージになります。

取り組む上での課題
R&Dに取り組むのは、簡単なことではありません。R&Dに取り組む上では、以下のようなリスクや課題と向き合う必要があります。
- 大きなコストがかかる
- 利益に繋がらないリスクもある(例:研究成果が出ない、他社に真似される)
- 相応しい人材の確保が難しい
R&Dに取り組む時に大きな課題となるのが、大きなコストがかかるのに、利益に繋がらないリスクもあるという点です。特に基礎研究などは、それがビジネスや利益に繋がるまでに何年もかかります。成果が出ない可能性もあり、しかも折角の研究結果が容易に他社に真似される可能性もあります。
R&Dに費やしたコストが回収できないリスクがあるため、大規模なR&Dには及び腰な企業も多いです。
また、高いレベルの研究開発ができる人材の確保も大きな課題です。優れた研究結果は億単位のビジネスに繋がるため、国内だけでなく海外の企業とも人材獲得競争をしなくてはなりません。
優秀な人材を見つけ、その人たちに選んでもらえるような待遇・研究環境を提供するのは容易ではありません。

R&Dに関わる部署・部門
R&Dに取り組む企業は多くありますが、体制や担当部署、またその組織の名称は様々です。
専門の部門を持つ企業も
大企業の場合、「研究開発部」「新規事業開発室」などR&Dのための専門部署を設けているケースが多いです。子会社・関連会社・研究所という形で、独立した組織になっているケースも珍しくありません。例えば以下のような例があります。
トヨタ自動車株式会社
トヨタはR&Dに力を入れている会社の一つであり、基礎研究を行う「豊田中央研究所」、先行開発を行う「東富士研究所」、ソフトウェアを中心とした新規技術・事業開発を行う「ウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社」など、国内だけでも様々な研究施設・組織があります。
また海外でもR&Dを行っており、例えばアメリカの「トヨタ・リサーチ・インスティテュート」では人工知能の研究を行っています。
(※出典:トヨタ自動車ホームページ「研究・開発拠点」)
富士フイルム株式会社
富士フイルムには、全社横断的な先端研究やコア技術の深耕・発展を担う「先端研究所」という組織があります。横断組織を作ることで、既存の技術分野や組織の壁を取り払った研究を目指しています。
富士フイルムでは、この先端富士研究所以外にも「ディビジョナルラボ」を事業部直下に置くなど、様々な組織でR&Dに取り組んでいます。
(※出典:富士フイルム株式会社ホームページ「研究開発」)

社長室や事業部がR&Dを行うことも
R&Dの規模が小さかったり企業そのものが小規模であったりする場合、独立したR&D組織が存在しないケースもあります。その場合、社長室や事業部の中で一部のチームが、新規事業の開発や既存サービスの改善に取り組むことが多いです。
また「常にR&Dに取り組んでいる訳ではない」という会社もあり、そうした企業ではプロジェクトとして期間限定で新商品開発に任命されるというケースも多いようです。
LiigaならR&Dに携われる求人を多数紹介
このように企業のR&Dに対する向き合い方は様々で、「どんな企業で」「R&Dの中のどの領域・仕事を担いたいのか」によって、探すべき求人や応募すべき部署が異なります。同じ企業でも所属によって研究開発の内容が大きく異なることもあるので、同じ会社の求人でも一件ずつ求人票に目を通してから応募することをおすすめします。

Liigaでは、以下のようなR&Dに関わることができる求人も数多く紹介しています。(※2022年度掲載求人より一部抜粋)
- 通信システム分野での新規ビジネス創出
- XRやメタバース技術の研究開発
- 細胞・遺伝子治療分野に関する研究開発
- パーソナルケア領域での製品開発
- 美容や旅行領域でのプロダクト開発ディレクター
一口にR&Dといっても様々な研究フェーズ・研究領域があるので、まずは具体的な求人をチェックしてみてください。