sponsored by A.T. カーニー
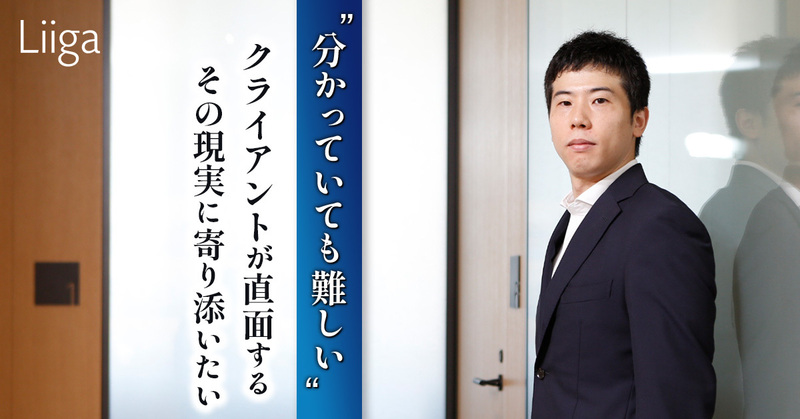
みずほ銀行でトレーダーとして勤務した後、現在はA.T. カーニーでコンサルタントとして活躍する早川純平氏。金融業界が変化を求められる中で感じた「もったいなさ」が、転職を志した理由の1つになっているという。また、伝統的な日本企業出身であることが、現在のコンサルティングの仕事にも役立っているとも語る。A.T. カーニーの魅力、そして自身の成長の軌跡と将来像について話を聞いた。
※内容や肩書は2023年12月の記事公開当時のものです。
長く停滞しているこの国の状況を変えたい
――まずはご自身のこれまでのキャリアを教えてください。
早川:私は大学院で数理統計学やコンピュータサイエンスの研究していました。もともと金融のトレーディングに興味があったこともあり、自分の専門も生かせる就職先として選んだのはみずほ銀行です。当時は主にデリバティブなどのトレーディング業務を担当していました。
仕事は面白かったのですが、3年ほど続ける中で、機械学習やAIをトレーディングに取り入れることで人が関わる業務が徐々に少なくなっていたんですね。業界全体に目を向けると、IT企業がどんどん参入し始めて、伝統的な金融機関が苦しくなるという状況も生まれていました。
みずほ銀行に限らず、金融業界には優秀な人材が多く集まっていることは間違いありません。しかし、比較的守られた環境にいたために、新しいテクノロジーにどう対処すべきかわからず停滞してしまっている。これは金融業界だけでなく国内全体の問題だと思うのですが、そうした状況を非常にもったいないと感じていました。決して“人”が悪いのではない、何らかの“環境要因”が日本経済を足止めしているのではないか。コンサルティングファームへの転職を考えるようになったのは、この問題の解決に貢献したいという気持ちが強くなっていったからです。
――コンサルティングファームの中でもA.T. カーニーを選んだ理由は何でしょうか?
早川:大きく2つあると思っています。1つ目は、A.T. カーニーの面接官の皆さんから、日本を良くしていこうというパッションを強く感じたこと。これはもともと自分がコンサルを志望した理由とも重なるので、非常に引かれたポイントです。
そして2つ目は、面接の過程で私個人を見てくれていると感じたこと。問題解決能力を測るケース面接は他のファームと変わらないのですが、それとは別にビヘイビアを見る面接がありました。その人がどんな価値観で仕事に取り組んできたのか。これからどうしたいのか。「誰でもいいから仕事ができそうな人に来てもらう」のではなく、早川という人間の人となりも含めて評価していただきました。そこが決め手だったと思います。
――未経験からのチャレンジで苦労したことはありますか?
早川:これはちょっと参考にならないかもしれませんが、実は苦労という苦労は経験していないんですよね。頭の使い方についても、コンサルファームだから特殊なことをするというわけではなく、問題解決をする際の自然な思考法だと思うので、前職とのギャップもそこまで感じていません。それと、A.T. カーニーは役職に関係なくフラットな議論ができる風土があるので、最初から思ったことを言えたというのも苦労を感じなかった理由だと思います。
「自分ごと」としてプロジェクトに取り組む
――昇進も早かったとお聞きしていますが、どんな意識で仕事に取り組まれてきたのでしょうか。
早川:入社6年目でプリンシパルなので、たしかに昇進は早い方かもしれません。ただ、自分自身としては何か特別なキャリアイメージがあったわけではなく、あくまでも目の前の仕事に一生懸命取り組んできた結果だと思っています。意識したことといえば、どの役職にいる時も、アサインされたプロジェクトに対して「自分ごと」として取り組んできたことでしょうか。与えられた範囲でそれなりにやればいい、というスタンスでは高い評価を得ることは難しいと思います。
やはり、常にチャレンジ精神を持って仕事に向き合うことは大切ですよね。経験を積んで慣れてくると、同じことをやった方が不安もないし結果も出しやすいのですが、今より成長した自分をイメージして、できる限り負荷の高い選択をするようにしていました。
もう1つ挙げるとすれば、先輩たちの良いところを真似したことでしょうか。資料のまとめ方やプレゼンテーションのやり方。私たちコンサルタントは、時にクライアントにとって耳の痛いこともお伝えしなければなりません。例えば「組織の欠点」を言いたい場合「組織のクセ」という表現を使うことで、クライアントに前向きに受け止めてもらうことができます。些細なことだと思うかもしれませんが、当時の私には大きな違いだと感じたんです。自分がいいなと感じる部分は積極的にまねすることで、より早く成長できたと感じています。
――組織の風土や制度面で、成長の後押しとなったものはありますか。
早川:先ほど申し上げたように、当社は役職に関係なくフラットに議論できる風土があります。A.T. カーニーの場合、役職はヒエラルキーではなく単なる役割の違いという印象です。ヒエラルキーだと偉い人が言うことが正しいという話になりますが、役割の違いなので誰でも遠慮なく思ったことを発言できる。だからこそ、個々人の良さが存分に引き出されると感じています。それに加えて、任せるカルチャーも若手の成長を強力に後押ししてくれるのではないでしょうか。
制度面では、メンターの存在も大きかったですね。コンサルタントはプロジェクト単位で動くので、その都度フィードバックはもらえるのですが、キャリアの悩みなどを話す機会はあまりありません。そこを補うためにメンター制度がありまして、メンターにはプロジェクトと関係ない先輩がついてくれるので、色々な相談をすることができます。役職も上の方なので目線が高く、自分の視座も引き上げてもらえる。私にとっては非常にありがたい制度でした。
トレーダー時代に意思決定した経験が、今も役立っている
――仕事の中で、前職の経験が生きていると感じる部分はありますか?
早川:まず大きいのは意思決定の部分ですね。前職はトレーディングをしていたので、不確実な状況の中でも自分なりの仮説を持って意思決定する必要があったのですが、それはコンサルの世界も同じです。“正解”のない中で考え抜き、自分自身の思いを基に意思決定する。このスタンスはトレーディングの経験から学んだことだと思っています。
もう1つは、いわゆる典型的な日本企業にいたので、組織の力学や物事の決まり方を身を持って知っていることです。日本の企業は必ずしもロジックだけで動いているわけではなく、人間関係や部署間のパワーバランスなど、さまざまな組織力学が意思決定に影響しています。
クライアントに変革をもたらそうとする場合、ここはとても重要な点で、あるべき姿を実現するには何がドライバーになるのかを見極める必要があります。それは数値によるロジックやエビデンスではなく、影響力のある誰かの一言かもしれません。柔軟に組織を運営するためには不可欠な考え方ですが、ある意味では合理的でない世界であることも事実でしょう。そうした現実があることは、伝統的な金融機関にいたことで腹落ちできたし、それを踏まえた上で仕事ができるのは前職の経験が生きている部分だと感じます。
――組織変革のプロジェクトでは、どんなことを心がけているのでしょうか?
早川:クライアントの経営陣の皆さんは、今何をするべきかということはおぼろげながら理解されているケースが多い。しかし、分かっていても実行できない何らかの理由があるわけです。「分からない」よりも「できない」問題の方が大きいということを、さまざまなプロジェクトを通して実感しています。
多くのコンサルタントは「何をすべきか」というWhatを語りたがりますが、クライアントにとっては「どうすれば実現できるか」というHowの方が重要なんだと強く意識するようになりました。
――これまで担当された中で、特に印象深いプロジェクトはありますか?
早川:医療機器メーカーの営業改革プロジェクトが印象深いですね。そのクライアントは、従来は個々の営業パーソンの力量で売り上げを維持してきたのですが、市場が成熟してきたために他社とパイの奪い合いになり、思うように売り上げが伸びていかない。そこで私たちが入らせてもらうことになり、まずは現状をどう認識しているかについて、営業部の皆さんに話を聞いていきました。
すると、人によっては危機感を持っている方もいるし、逆にまだ会社は悪くないポジションにいると考える方もいる。さまざまな意見が出て、それらをまとめながら組織としての共通認識を作り、今後何をどう改革するべきなのかを定めていきました。ただ、それも「こうあるべき」という理想論を振りかざすだけでは何も変わりません。従来のやり方も踏まえ、どうすれば真の改革を実現できるかを深く議論しながら落とし込んでいきました。
先ほどお話したように、やはり分かっていてもできない現実がありますから、そうした思いもくみ取りながらクライアントの最適解を探して一緒に伴走する。これは今も続いているプロジェクトですが、組織変革の典型例として印象に残っています。
――今後の目標をお聞かせください。
早川:多くのクライアントから気軽に相談される人になりたいですね。プロジェクトはお客さんを支援する1つの形ではあるのですが、具体的なプロジェクトにならなかったとしても、困ったときには早川に相談してみようと思ってくれるようなクライアントを増やしていきたい。自分の会社を良くしたいという熱い気持ちを持ったお客さんの輪を広げて、それが伝播していけば、日本全体を良くしていけるはず。そんなパッションを持ち続けて仕事をしていきたいと思っています。


