sponsored by Wonder Camel
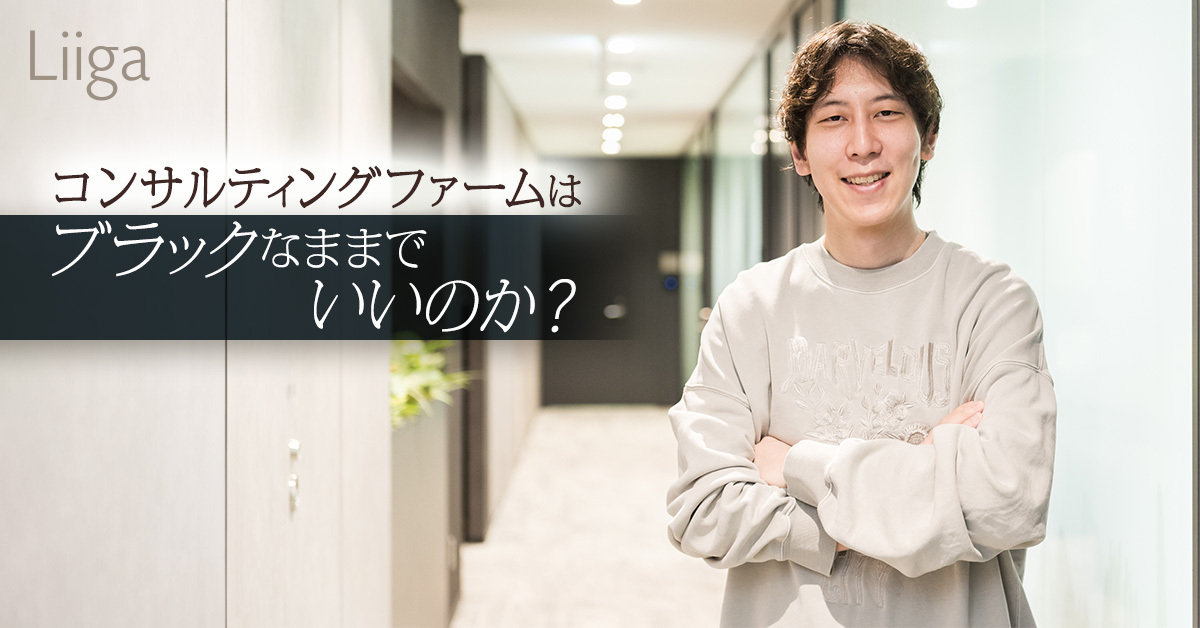
深夜まで働くことが当たり前だった日々。壮絶な80連勤を経験したことも——。自身のコンサルティングファーム勤務時代を振り返りながら、Wonder Camel創業者の和田淳史氏は変わらないコンサル業界の現状に疑問を投げかける。
たどり着いたのは、稼働時間を減らしながら収入を大幅に増やせる「成果報酬型」の働き方と、それを実現する独自の商流だった。社員のワークライフバランスが充実するのは成果の一端に過ぎない。和田氏が目指すのは、コンサルタントを真に持続可能な職業に変えて業界を発展させること。その言葉には、ポストコンサルのキャリアを考える上で大きなヒントが詰まっていた。
※内容や肩書は2024年5月の記事公開当時のものです。
同条件のプロジェクトで、他社の倍近い報酬が得られることも
——Wonder Camelでは、コンサルティングファームでは見られない独自の成果報酬型の制度を導入していると聞いています。その概要を教えてください。
和田:まず、当社はいわゆるコンサルティングファームとは商流が大きく異なります。
一般的なコンサルティングファームでは、パートナーなどの“上位層”が顧客企業から案件を獲得して、自社内でチームを組成し、プロジェクトを動かしていきますよね。Wonder Camelの場合はそのコンサルティングファームが顧客なんです。当社のコンサルタントには、顧客である契約先コンサルティングファームのプロジェクトに加わってもらいます。
コンサルタントへはその成果に応じて、顧客のコンサルティングファームから受け取る単価の中でかなりの割合を報酬として支払っています。場合によっては単価の半分近くが報酬になることもあります。
——顧客からの単価の半分近くが報酬に。これは大きなインパクトがありますね。
和田:例えば、顧客企業がコンサルタント1人あたりに月400万円の単価を支払っているケースがあるとします。一般的なこの業界の相場観で考えると、コンサルタント本人の報酬として残るのは100万円程度ではないでしょうか。
これでも多い方かもしれませんね。大手ではオフィス代や教育投資に割かれますし、外資系の場合は400万円のうち3割ほどがグローバル本体に吸収されることもあるでしょう。同じ条件でWonder Camelなら、コンサルタントに180万円程度と倍近い報酬を渡せます。
——なぜこれだけの報酬を実現できるのでしょうか。
和田:私が大手コンサルティングファームを2社経験しており、業界内の意思決定権者との豊富なつながりを持っていることが大きいです。今はどこのコンサルティングファームも人材不足で苦しんでいるため、案件数は非常に多いと感じます。そのためコンサルタント個人の稼働率が安定しており、その人がもたらしてくれる売り上げも簡単に算定できるので、単価の大部分を報酬に充てても問題がないのです。
また、当社はコンサル経験者を中心に採用していることから、教育にはそれほど多くの費用を使っていません。
ビジネスモデルとしてはテック業界のSES(受注型・受託型でエンジニアの技術力を提供するサービス)に近いのかもしれませんが、国内のコンサルティングファームで、コンサルタントに成果報酬型の制度を導入している例はほとんどないと思っています。そもそも私たちのように、コンサルティングファームと直接一次請けの立場として取り引きすること自体が非常に難しく、参入障壁がとても高いです。私は各社の役員との直接のつながりがあるのでこの壁を突破できました。
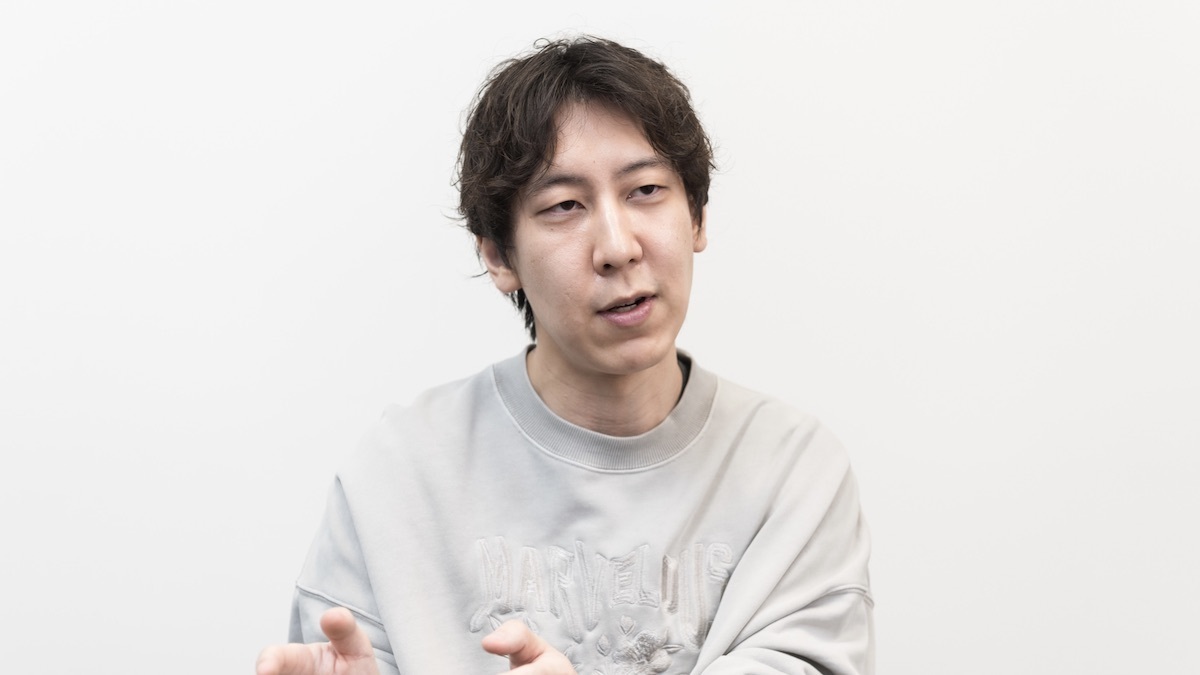
ギリギリの状況で仕事にも家庭にもコミット。コンサル業界の現実
——同業のコンサルティングファーム出身である和田さんがなぜこのビジネスモデルにたどり着いたのか、とても気になります。
和田:成果報酬制度はWonder Camel創業と同時に始めました。端的にいえば、「人に寄り添う会社」をつくりたかったんです。
自分の半生を振り返ってみると、私は困っている人、努力している人の助けになることが好きでした。学生時代もそうです。私はマクロ経済などの勉強が好きで真面目に取り組んでいたのですが、友人たちの中には音楽や麻雀に夢中になって、ろくに授業に出ない人もちらほらいましたね。試験の時期が近づくとそんな友人たちに泣き付かれて、私はよく予想問題集や解答集を作っていました。
大学卒業後にコンサル業界へ進んだのも、幅広い視点とスキルを身に付けて、困り事を抱える業界や個人に貢献したいと考えたからなんですよ。
——前職以前のコンサルティングファーム時代には、どんなプロジェクトに取り組んでいましたか。
和田:新卒で入社したアビームでは、長くSAPのプロジェクトに携わっていました。ある程度キャリアを積み、プロジェクトのマネージャーレベルを務められるようになった段階で「企業全体のコンサルティングに従事したい」と考え、BCGへ転職したんです。そこでは大手企業の組織課題解決や戦略策定などに携わりました。
——コンサルタントとして着実にステップアップしていったのですね。
和田:一方ではコンサル業界特有の長時間労働に苦しんでいたのも事実です。これはどこか特定の企業を批判したいわけではなく、業界全体にいまだ横たわっている問題だと思っています。働き方改革の波はコンサルの世界にも着実に広がっていますが、過酷な勤務を強いられている現場がまだまだあると感じます。
私の例でいえば、平日は夜中まで働き、翌朝も早くから動き出す日々でした。海外に赴いたプロジェクトでは80連勤したこともあります。
独身の私はそれでも何とかやっていけましたが、家族を持つ先輩は本当に大変そうでした。無理もないことだと思います。仕事ではプロジェクト全体の管理に追われるギリギリの状況の中、プライベートでは子育てや家事にもコミットしなければならないのです。
中にはプライベートを重視して仕事に一定の見切りをつけ、毎日午後6時に退勤する先輩もいました。でもその働き方だと、なかなか出世できなかったり収入が増えなかったりします。そんな現実に直面して、「コンサル業界で困っている人を助けたい」と強く思うようになりました。これがWonder Camel創業の原点です。
ワークライフバランスに加え、案件の魅力も充実していく
——コンサルタント個人にとって、Wonder Camelの働き方にはどんなメリットがあるのでしょうか。
和田:私が目の当たりにした先輩たちのように、ライフステージに合わせて働き方を見直したいと考えているコンサルタントは少なくないでしょう。
朝から深夜まで働くことが珍しくない業界で、役職者になれば人材採用活動やCSR活動などの部門共通の活動がミッションに加わることもあり、プライベートの時間の確保がますます困難になっていきます。しかし当社であれば本業のコンサル以外のことにタッチする必要はありません。
また、当社の社員は顧客であるコンサルティングファームとの契約上、労働時間の上限が明確に定められています。どんな事情があっても顧客は決まった時間以上に当社の社員を働かせることができません。事前に取り決めた月間労働時間が守られるので、必然的にワークライフバランスが向上します。それでいて報酬は前職を大きく上回ることもあります。
——「刺激的な案件に出合って成長したい」と考えている人も多いと思います。そうしたコンサルタントの希望もかなうのでしょうか。
和田:案件数が豊富なので、個々人の希望する領域に沿って案件を選べる状況です。ある程度の専門性を持ち、さらに深めていきたい領域を持っている人には、その得意分野で活躍してほしいですね。
自ら独立するほどのリスクはまだ取れないけれど、今よりも収入を増やしたい。そんなコンサル業界の中堅層には最適な環境かもしれません。社員としてある程度守られながら、成果に応じた報酬を得られるようになります。
ただ、報酬は個人の単価次第なので、コンサルタントとしての実力がシビアに問われることを覚悟してほしいです。希望する案件に入れたとしても、プロジェクトで成果を出せなければ顧客側は単価を絞る動きになるでしょう。だからこそ私たちは「成果報酬」という言い方をしています。
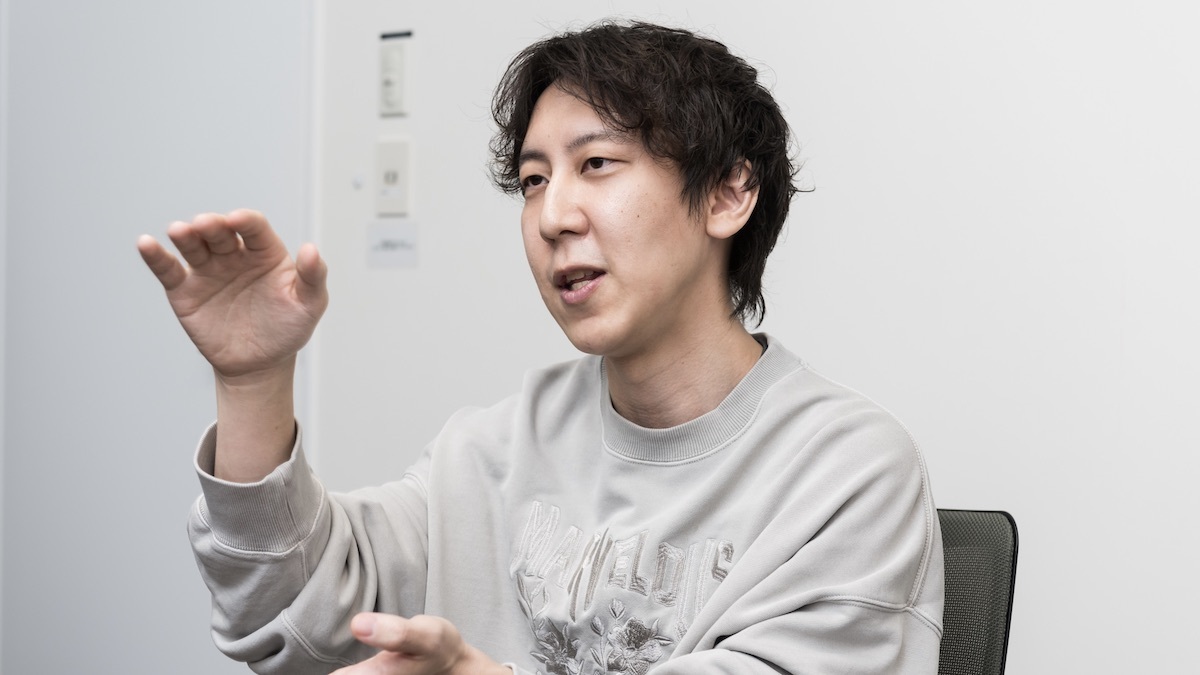
DX関連案件が急増。現在のWonder Camelで即戦力になれる人材とは
——Wonder Camelに向いているのはどんな人でしょうか。
和田:自分の働き次第で単価が変わり、それがダイレクトに報酬に反映される。そしてプライベートの時間を充実させることもできる。ここに魅力を感じるコンサルタントは当社に向いていると思います。
一方、Wonder Camelでは大手コンサルティングファームのように数十億円規模のプロジェクトを自ら動かすことはできません。仕事の規模感を求めるなら、一次請けである大手コンサルティングファームに身を置くべきでしょう。
——スキル、経験の面ではどうでしょうか。
和田:直近では、事業会社のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進プロジェクトに関する案件が急増しています。大手企業向けにSAPやセールスフォースなどのパッケージシステムを導入する経験や、大規模システムのPMO(Project Management Office)の経験を有する人なら、即戦力になり得ます。
先ほど、採用業務に携わる必要はないと言いましたが、経験豊富な人であれば、メンバーを受け持って育成を担ってもらう可能性もあります。当社の新卒メンバーや、社外の若手フリーランス人材とタッグを組んで動くようなケースです。こうした場合はプロジェクトによる報酬とは別に、人材育成に関する報酬も支払っています。
経験が浅い若手も、高スキルの方と組んで直接ナレッジを学んだり、社員全員が集まるナレッジ共有会に参加したりして成長できるはずです。当社はまだ小規模なので大手のようなナレッジプラットフォームは整備できていませんが、プロジェクトベースで人を配置できる柔軟性を生かして個々人の成長を支援していきたいと考えています。
SAPやデジタルに興味がある人は未経験でも採用していますし、元コンサルに限らず、IT領域出身の社員も活躍しています。
——可能な範囲で、収入例も聞きたいです。
和田:大手総合コンサルティングファームのマネージャークラスを務め、大手企業向けにSAPの提案などを手掛けていた人のケースだと、前職年収の約800万円から当社転職後に約1600万円になりました。
人によっては、単価ベースで月300万円、年収ベースで2000万円を超えることもあります。また、5年目の若手が年収1300万円を超えている例もあります。実力本位の仕組みなので、年齢にかかわらず収入を伸ばすことができます。
ポストコンサルの転職で「同領域は避けた方がいい」理由
——自らの実力次第で報酬が上がっていくのは大きなメリットですが、その経験値を重ねれば重ねるほど、かつての和田さんのように自ら独立を目指す人も増えていくのではないでしょうか。
和田:そうですね。将来的には、どんどん独立してくれて構わないと思っています。コンサル業界や周辺業界で活躍してもらえれば、私たちもずっとつながっていられますから。
独立を果たすレベルになった人には高い信頼と実績、そして人がついてきます。そうした人材の独立を当社が支援することで業界内のプロフェッショナルが増え、結果的には当社の評判も高まるはず。そんな思いから、強い独立志向を持つ方の入社も歓迎しています。
——これからポストコンサルのキャリアを歩む人に向けて、アドバイスをお願いします。
和田:これはあくまでも私個人の考えに過ぎませんが……。
仮に収入がアップするとしても、同じ仕事をするために競合のコンサルティングファームに転職するのは、やめた方がいいかもしれません。やること自体は変わらないのに、一緒に動くメンバーは総入れ替え。働く時間が短くなることは少ないし、むしろ採用などの間接業務が増えるかもしれません。
報酬が少し増えただけで、仕事はもっと忙しくなるかもしれません。上が詰まっていて昇進が難しい……そんな“転職失敗例”もたくさん聞いてきました。
コンサルtoコンサルで動くなら、取り組む領域を大きく変えるか、働き方を大きく変えるべきです。それが私の持論です。後者を望む人のためにWonder Camelという場所をつくりました。
自分の稼働時間を減らしながら収入を増やすことができれば、新しい領域に挑戦する心の余裕が一気に広がると思います。そんな価値を生むポストコンサルのキャリアに挑戦してほしいですね。
