転職エージェントはやめとけって本当?使うなと言われる理由と見極め方
2024/09/04
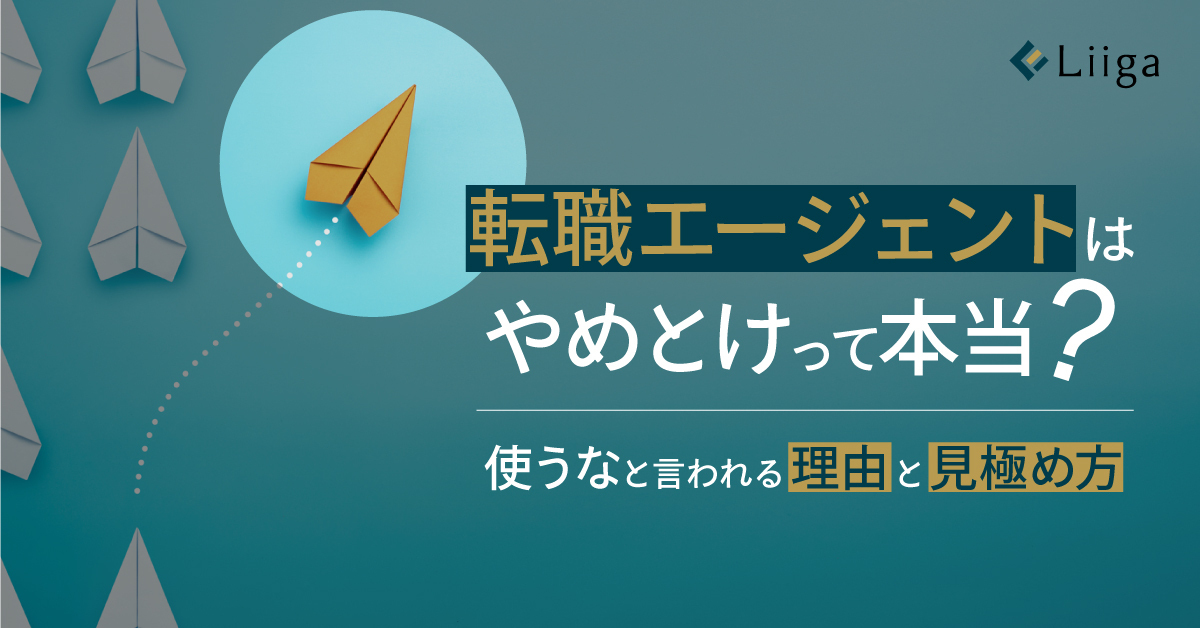
転職エージェントについては否定的な意見も見られますが、必ずしも「利用しない方が良い」とは限りません。むしろメリットも多く、活用方法も多様です。
ここでは「転職エージェントを使うな」と言われる理由や利用すべきでない転職エージェントの特徴、転職エージェント利用のメリット、そして見極めのポイントを分かりやすく解説します。
【目次】
転職エージェントは使わない方がいい?
インターネット上で「使うな」「やめとけ」といった意見も見られる転職エージェント。
これらはあくまで一意見であり、必ずしも「使わない方がいい」とは言えません。ただし、以下のように注意すべき点があるのも事実です。
- 転職エージェントの利用には向き不向きがある
- 信頼できない転職エージェントもいる
「転職エージェントを頼るべきか否か」は、その人の性格や達成したい目的、目指すキャリアの方向性などによって異なります。まずは、自分に合ったキャリア形成の方法を考えましょう。
そのうえで、転職エージェント利用では「誰に支援してもらうか」の見極めが非常に重要です。
「転職エージェントを使うな」と言われる理由4つ

そもそも転職エージェントを「使うな」「やめとけ」と言われる主な理由は、以下の通りです。
🔐この先は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
コラム作成者
外資就活ネクスト編集部
外資就活ネクストは、「外資就活ドットコム」の姉妹サイトであり、現役プロフェッショナルのキャリア形成を支援するプラットフォームです。 独自の企画取材を通して、プロフェッショナルが必要とする情報をお伝えします。
続きは会員登録後(無料)にご覧いただけます