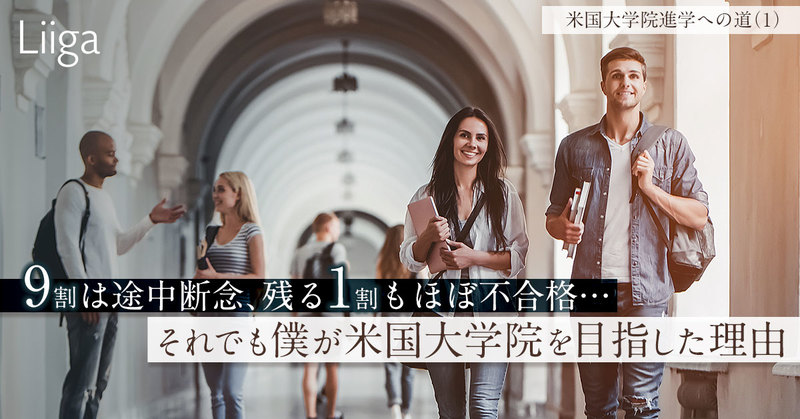
はじめまして、勝山湧斗と申します。
2020年3月に東北大学工学部を卒業し、同年秋よりUniversity of California, Los Angeles(カリフォルニア大学ロサンゼルス校、以下UCLA)の大学院(5年間の博士課程プログラム)に進学します。
今回、Liigaで米国大学院受験に関する連載を始めることになりました。この連載では、
・米国大学院に進学するメリット ・進学のハードルの高さ ・米国大学院受験で審査される項目 ・それらの項目への具体的な対策
などを、私の個人的な経験と、私の周囲の方々の経験に基づいて書いていく予定です。
初めに断っておくと、残念ながら、唯一の絶対的な受験ノウハウは存在しません。米国の大学院受験は日本のようにペーパーテストだけでは決まらず、研究能力や文章力、プレゼンテーション能力、熱意などを総合的に判断されるからです。
100人いれば100通りの大学院受験の戦略があります。つまり、自分に合った戦略を立てることが重要です。そのためにすべきことは情報収集です。できるだけ多くの情報、多くのパターンを知ることです。
その一例として、帰国子女でなく、英語が得意でもない日本人の私が立てた戦略について書いていきたいと思います。
・留学で気づいたアメリカに集まる学生のレベルの高さ
・アメリカでなら恵まれた環境でレベルの高い研究ができる
・米国大学院は授業料がかからない!?
・進学への大きな壁―9割は諦め、残りの1割は出願してもほぼ落ちる
留学で気づいたアメリカに集まる学生のレベルの高さ
初回は「米国大学院に進学するメリット」と「進学のハードルの高さ」について書かせていただきます。
まず、私は米国大学院への進学のメリットは大きく3つあると思っています。
1つ目は世界から集まってきた優秀な学生たちと切磋琢磨しながら学べること。
2つ目は最先端の研究ができること。
3つ目は授業料がかからないどころか給料がもらえること。
それらのメリットに気づいたのは、大学2年生のときに行ったUC Berkeley(University of California, Berkeley、カリフォルニア大学バークレー校)への交換留学がきっかけでした。私は当時、東北大学の化学・バイオ工学科に所属しており、また国際交流団体で異文化交流の楽しさを知ったこともあって、思い切って世界81カ国に所在する研究大学1,500校の学術研究および評判を総合評価したU.S. News & World Report Rankingの化学部門で1位だったUC Berkeleyに1年間交換留学することに決めました。
留学期間中に感じたのは、世界から集まってきた優秀な学生たちとともに学べる環境があるということです。
UC Berkeleyにいた学生たちは英語も堪能で、授業の理解もとても早く、非常に驚かされました。学部3年生なのに「Nature」や「Science」などの有名な学術雑誌に論文を投稿したことがある学生や、国際学会で受賞したことがある学生に出会いました(分野にもよりますが、日本では修士課程でも国際学術雑誌に論文を投稿する人はまれだと感じます)。

さらに驚いたことは、UC Berkeleyで研究をしている日本人の大学院生や研究者は、日本を代表するような優秀な方々ばかりであること。世界中からそういう人たちが集まっている大学院は学部と比べて更にレベルが高いことがわかりました。
私は東北大学では、成績はほとんどAAであり、いわゆる優等生の部類に入っていた自負があったのですが、UC Berkeleyでは劣等生でした。授業も完全には理解できず、ディスカッションでも自分の意見を言えず、ほとんどの余暇時間を宿題に費やしました。それでも授業についていくのが大変でした。こんなにも無力さを感じたのは初めての経験でした。
また、最もリベラルな大学とうたわれるUC Berkeleyを存分に味わうために、専門外である“intercultural communication(異文化間コミュニケーション)”の授業も履修しました。
講義の性質上、学生の多様性が高く、白人、黒人、アジア人、ヨーロッパ人など合わせて25人程度で構成されており、日本人は私1人でした。毎回異なるトピックについて全体で輪になってディスカッションするのですが、なかなか声を上げて自分の意見を全体に伝えることができず、何度も悔しい思いをしました。
ある日は「エロ」が議題の授業でした。クラスメートは恥じらうことなく自分の意見をぶつけ合い、熱心に議論をしていました。日本でしか過ごしてこなかった私にとって今まで考えなかったような意見がたくさんあり、多様性の中で生きる実感を得ることができました。
もしこういった環境で学び続け、現地の学生と対等に議論できるようになれば、世界で活躍する人材になれるのではないかと感じました。
余談ですが、現地のストリートダンスのチームに所属したことで、国籍や言語の壁を越えてチームが1つになった感覚が味わえたことも、留学ならではの経験でした。
アメリカでなら恵まれた環境でレベルの高い研究ができる
2つ目のメリットは、先に述べた通り、米国の大学院なら最先端の研究ができるということを実感したからです。
🔐この先は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。