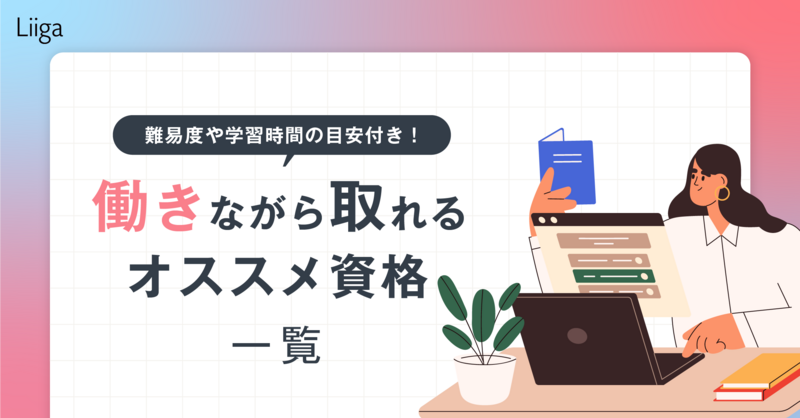
スキルアップや昇進・昇給、転職などのために「働きながら資格を取得したい」という人は多いです。
ここでは働きながら取得できるオススメ資格をご紹介しています。試験の実施回数や合格率、難易度、学習時間の目安なども解説していますので、参考にしてください。
働きながら取れるオススメ資格一覧
ここでは、より多くの人が自分に合う資格を選べるよう、難易度の異なる資格を16種類ご紹介します。オススメ資格とそれぞれの難易度は、以下の通りです。
| 番号 | 資格/試験 | 種類 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| ① | 危険物取扱者(乙種4類) | 国家資格 | ★ |
| ② | ウェブデザイン技能検定 | ★ | |
| ③ | ITパスポート | ★★ | |
| ④ | ファイナンシャル・プランニング技能士 | ★★~★★★ | |
| ⑤ | 宅地建物取引士 | ★★★ | |
| ⑥ | 管理業務主任者 | ★★★ | |
| ⑦ | 行政書士 | ★★★★ | |
| ⑧ | 中小企業診断士 | ★★★★★ | |
| ⑨ | 販売士 | 公的資格 | ★ |
| ⑩ | 色彩検定 | ★~★★ | |
| ⑪ | ビジネス実務法務検定 | ★~★★ | |
| ⑫ | マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) | ★~★★ | |
| ⑬ | 日商簿記検定 | ★★~★★★ | |
| ⑭ | 登録販売者 | ★★★ | |
| ⑮ | 秘書技能検定 | 民間資格 | ★~★★ |
| ⑯ | TOEICⓇListening & Reading Test | ★★★~ |
次の章からは、各資格の概要を解説しています。試験の合格率や学習時間の目安などもご紹介していますので、参考にしてください。
働きながら取れるオススメ国家資格8種類
国家資格は、法に基づいて個人の能力や知識を証明する資格です。
文部科学省では、国家資格について「法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い」と紹介しています。
※引用元:文部科学省「国家資格の概要について」
①危険物取扱者(乙種4類)
| 実施頻度 |
年2回~ ※地域による |
|---|---|
| 合格率 | 約30~35% |
| 難易度 | ★ |
| 学習時間の目安 | 40~60時間 |
危険物取扱者は、消防法に定められている危険物の取扱いやその立ち合いに必要な国家資格です。ガソリンスタンドや化学工場、石油貯蔵タンク等の施設で働くのに役立ちます。
資格は甲種・乙種・丙種の3種類があり、このうち乙種と丙種は特別な受験資格がありません。なかでも「乙種4類」はガソリンや灯油、経由、重油などの引火性液体を扱える資格で、需要が高いです。
②ウェブデザイン技能検定
| 実施頻度 |
年4回(5月、8月、11月、2月) ※2~3級の場合 |
|---|---|
| 合格率 |
2級:約30~40% 3級:約60~70% |
| 難易度 | ★ |
| 学習時間の目安 |
2級:30~60時間 3級:20~30時間 |
ウェブデザイン技能検定は、Web制作に必要な知識や技能を問う試験です。合格すると「ウェブデザイン技能士」を名乗ることができます。
レベルは1~3級の3段階あり、3級は誰でも受験可能です。入門レベルの内容なので、「企業でWeb担当になった」「今後Webデザインの仕事をしてみたい」といった場合に受験をお勧めします。
一方2級以上では、受験資格として実務経験などが必要です。

③ITパスポート
| 実施頻度 | 随時 |
|---|---|
| 合格率 | 約50% |
| 難易度 | ★★ |
| 学習時間の目安 | 100~150時間 |
ITパスポートは、ITに関する基礎的な知識を証明する国家資格です。AIやアジャイル開発をはじめとする技術・手法の概要、セキュリティやネットワークの基礎知識などが出題されます。
IT系の資格としては入門レベルで、近年は毎年約20万人が受験しています。試験は全て4択問題です。三菱商事や三井物産の内定課題になるなど、IT企業に限らず取得を求められることがあります。そのため取得する資格が決まらない人にもおすすめの資格です。
④ファイナンシャル・プランニング技能士
| 実施頻度 |
年3回(5月、9月、1月) ※2~3級の場合。2級は2025年度よりCBT導入 |
|---|---|
| 合格率 |
2級:約25~35% 3級:約70 ~75% |
| 難易度 | ★★~★★★ |
| 学習時間の目安 |
2級:150~300時間 3級:80~150時間 |
FP(ファイナンシャル・プランニング)技能士とは、税金や投資、保険、ローン、年金など「お金」に関する知識を有し、アドバイス等を行える存在です。FP技能士としての知識やスキルがあれば、金融機関や不動産業界に限らず社員の給与管理などを行う総務部や人事部、経理部でも重宝されます。
試験は学科試験と実技試験があり、学科試験は4択のマークシート方式、実技試験はマークシートまたは記述式の問題です。
3級は初心者でも取り組みやすいですが、仕事で活かしたいなら最終的には2級以上を目指すと良いでしょう。
⑤宅地建物取引士
| 実施頻度 | 年1回(10月) |
|---|---|
| 合格率 | 約15~17% |
| 難易度 | ★★★ |
| 学習時間の目安 | 300時間 |
宅地建物取引士(宅建士)は不動産取引の専門家であり、不動産業界で働くには欠かせない資格です。
契約前に行う重要事項の説明など、宅建士だけが行える独占業務もあります。また宅地建物取引業法では、宅建業を営む事務所において「従業員5名につき1名以上」の専任宅建士(※成年者)の設置義務を定めています。
試験は4択のマークシート方式で、合格後は2年の実務経験または実務講習の受講が必要です。
⑥管理業務主任者
| 実施頻度 | 年1回(12月) |
|---|---|
| 合格率 | 約19% |
| 難易度 | ★★★ |
| 学習時間の目安 | 300時間 |
管理業務主任者も不動産系の資格で、マンションを扱う場合に重宝されます。管理委託契約時の重要事項の説明や、組合に対する管理状況の報告などを行える資格です。
試験方式は4択のマークシートです。試験合格後の登録には2年の実務経験が必要ですが、登録実務講習の受講で代替することもできます。また管理業務主任者に合格していると、より難易度の高い「マンション管理士」の試験が一部免除となります。

⑦行政書士
| 実施頻度 | 年1回(11月) |
|---|---|
| 合格率 | 約10~12% |
| 難易度 | ★★★★ |
| 学習時間の目安 | 800時間 |
行政書士は、司法書士とともに「街の法律家」と言われる国家資格です。具体的には、国や地方自治体などの官公署に提出する書類の作成や提出の代行、書類作成に関するアドバイスなどを行えます。
ここまでご紹介してきた資格に比べて難易度が大幅に上がりますが、法律系の国家資格においては「易しい」レベルと言えます。転職に役立つだけでなく、独立開業に繋げられる点も魅力です。
⑧中小企業診断士
| 実施頻度 | 年1回(8月~) |
|---|---|
| 合格率 | 約3~8% |
| 難易度 | ★★★★★ |
| 学習時間の目安 | 800~1,000時間 |
中小企業診断士は経営コンサルタントに関する唯一の国家資格で、中小企業の経営課題に対応するための診断や助言を行います。企業経営に関する知識の証明になり、将来的な独立だけでなく、昇進や転職にも役立ちます。
資格取得にはマークシート形式の1次試験、筆記・口述での2次試験、さらに実務補修、実務従事を経なければいけません。1次・2次試験ともに合格率は20%程度で、働きながら取得するのはかなり大変です。しかしながら、その分だけ取得後のメリットが大きい資格とも言えます。
働きながら取れるオススメ公的資格6種類
公的資格とは、民間団体や公益法人が実施している中で、各省庁や大臣などから認定を受けている資格です。国家資格に準ずる信頼性があり、知名度の高い資格も多くあります。
⑨販売士
| 実施頻度 | 随時 |
|---|---|
| 合格率 |
2級:約55~70% 3級:約55~70% |
| 難易度 | ★ |
| 学習時間の目安 |
2級:60時間 3級:30時間 |
販売士は、商品知識や販売技術、仕入れ、在庫管理、マーケティングなど「販売」に関する知識を証明できる資格です。1〜3級の3段階があり、3級は「売り場の販売員」、2級は「売り場の管理者クラス」、1級は「店長・経営者」レベルに相当します。
取得は比較的簡単ですが、資格そのものには5年間の有効期限があります。販売店によっては社員教育の一環として取得を義務付けているケースもあるようです。
⑩色彩検定
| 実施頻度 |
年2回(6月、11月) ※1級のみ年1回 |
|---|---|
| 合格率 |
1級:約50% 2級:約75% 3級:約75% UC級:約90% |
| 難易度 | ★~★★ |
| 学習時間の目安 |
1級:150時間 2級:50~100時間 3級:15~30時間 UC級:15~30時間 |
色彩検定は「色」に関する知識や技能を問う試験で、ファッション業界やインテリア業界、出版・広告業界、建築業界などで役立ちます。また、自社のWeb制作や商品開発といった場面でも知識を活かすことができます。
レベルは1〜3級と、「色のユニバーサルデザイン(UC)」に関する知識を問うUC級の4種類があります。初めて受験する場合は3級からのチャレンジで構いませんが、履歴書等に書きやすいのは2級以上です。

⑪ビジネス実務法務検定
| 実施頻度 |
年2回(6~7月、10~11月) ※2~3級の場合 |
|---|---|
| 合格率 |
2級:約40~50% 3級:約75~85% ※今後難化の可能性も |
| 難易度 | ★~★★ |
| 学習時間の目安 |
2級:60~100時間 3級:45~60時間 |
ビジネス実務法務検定は、ビジネス場面で必要な法知識を問う試験です。法務に限らず営業、販売、総務、人事などの職種で必要な法知識を習得できます。法知識が必要となる部門やコンプライアンス意識の高い企業への転職では、資格が有利に働くことも多いでしょう。
上記の合格率は過去3年のデータから概算した数値ですが、2023年度に出題形式や問題のレベルが変わり、合格率が大幅に低くなりました。試験がこのまま難化する可能性もあるので、出題傾向を見極めてから受験するのも一手です。
⑫マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
| 実施頻度 | 随時 |
|---|---|
| 合格率 | 非公表 |
| 難易度 | ★~★★ |
| 学習時間の目安 |
一般レベル:30~80時間 上級レベル:40~100時間 |
MOS資格は、Microsoft Officeの利用スキルを証明する国際資格です。WordやExcel、Power Pointなどの基本スキルがあれば日々のパソコン業務に活かすことができ、学習の成果を実感しやすい資格としておすすめです。取得が企業の内定課題になっていることも少なくありません。
転職では、事務職などで有利になる傾向があります。
合格率は非公表ですが、「一般レベルで80%程度、上級レベルで60%程度」と言われています。
⑬日商簿記検定
| 実施頻度 |
年3回(6月、11月、2月) ※2~3級はCBTで随時受験可能 |
|---|---|
| 合格率 |
2級:約12~37% 3級:約30~45% |
| 難易度 | ★★~★★★ |
| 学習時間の目安 |
2級:200~350時間 3級:50~100時間 |
企業の経営活動の記録や計算、整理において必要とされる簿記の知識と技能を問う試験です。簿記や会計はあらゆる企業で必要とされるため、取得すれば昇進や転職にも役立ちます。特に経理職に就く上では、簿記2級以上を取得していることが望ましいです。
2級の合格率には幅がありますが、これは受験方式による違いです。過去2年の試験結果を見ると、2級では統一試験に比べてネット(CBT)試験の方が圧倒的に高い合格率となっています。
なお3級の合格率は、統一試験とネット試験で差がありません。
⑭登録販売者
| 実施頻度 |
年1回(8月~12月) ※地域によって実施時期は異なる |
|---|---|
| 合格率 | 約40~50% |
| 難易度 | ★★★ |
| 学習時間の目安 | 200~400時間 |
登録販売者は、薬局などで一般用医薬品の販売ができる資格です。薬剤師と異なり薬の調剤や第一類医薬品の販売はできませんが、薬剤師不足を補う存在としてドラッグストアなどで重宝されています。
資格取得に向けてはある程度の学習が必要ですが、取得すれば手に職を付けられます。試験もマークシート方式なので、比較的取り組みやすいでしょう。
働きながら取れるオススメ民間資格2種類
民間資格は法令等に基づいた資格でなく、各省庁や大臣からの認定もありません。しかし資格の種類は豊富で、なかには高い知名度を誇るものもあります。
⑮秘書技能検定
| 実施頻度 | 年3回(6月、11月、2月) |
|---|---|
| 合格率 |
1級:約25~35% 準1級:約40~45% 2級:約50~60% 3級:約60~75% |
| 難易度 | ★~★★ |
| 学習時間の目安 |
1級:150時間 準1級:60~120時間 2級:30~60時間 3級:20~40時間 |
秘書技能検定はビジネス場面で必要な基礎知識や技能、社会人に求められる一般常識やマナーを問う試験です。「秘書になる人が取る資格」という訳ではなく、取得することで社会人として必要な知識やマナーを身に付けていることが証明できます。事務職などで勤める上でも役立つ資格です。
レベルは4段階ありますが、一般に転職で有利になるのは「2級以上」と言われています。なお2〜3級はマークシートと筆記での試験、準1級以上は筆記試験に加えて面接が課されます。
⑯TOEICⓇListening & Reading Test
| 実施頻度 | 年12回前後 |
|---|---|
| 合格率 | - |
| 難易度 | ★★★~ |
| 学習時間の目安 | 100点アップで約200時間 |
TOEICは世界約160ヵ国で実施されている英語の試験です。TOEICの中にもいくつか種類がありますが、日本の企業では一般にリスニング力と読解力の指標となる「Listening & Reading Test」の結果が重視されています。
試験は4択のマークシート方式ですが、約2時間で200問と1問あたりの解答時間が短いです。日常生活に加え、ビジネスの場面で使われる単語が頻出します。
企業によって求められるスコアが異なりますが、650点あると「一定の英語力がある」と認められやすいです。

資格選びのポイント
「働きながら資格を取りたい」と思っても、どういった資格を取るべきか迷う人も多いでしょう。
資格選びでは、以下の3つのポイントを基準に選びましょう。
- 取得の目的と用途
- 資格の取得難易度
- 受験資格や有効期限の有無
取得の目的が昇進や転職の場合は、目指す役職や業界に合わせた資格を選びましょう。例えば転職の場合、資格によってその業界への意欲を示せたり、豊富な知識と経験の証明になったりします。
昇進や転職でも「何を取得すれば良いか分からない」という場合は、幅広い業界で人気のある語学系・IT系・金融系の資格がおすすめです。
取得の目的や用途以外でも、受験要綱をよく調べ、「そもそも受験できる資格か」「取得後何年まで目的の用途に使えるか」といったこともチェックしましょう。
教育訓練給付制度が使える資格も
資格取得にあたっては、国の「教育訓練給付制度」を活用できる場合があります。
これは、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・修了した人に対し、取得費用の一部が支給される制度です。通学や通信、eラーニングの約1万5,000講座を対象に給付金が支給されています。
| 種類 | 給付率 | 対象講座の例 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練 |
受講費用の最大70% ※年間上限56万円 |
・業務独占資格などを目指す講座(介護福祉士、看護師、保育士など) ・デジタル関係の講座(応用情報技術者、ITストラテジストなど) ・大学院/大学/短期大学/高等専門学校の課程(MBA、教職大学院など) ・専門学校の課程 |
| 特定一般教育訓練 |
受講費用の40% ※上限20万円 |
・業務独占資格などを目指す講座(介護支援専門員実務研修など) ・デジタル関係の講座(基本情報技術者など) |
| 一般教育訓練 |
受講費用の20% ※上限10万円 |
・資格取得を目標とする講座(TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士など) ・大学院などの課程(修士・博士の学位などの取得を目指す課程) |
仕事と学習を両立する3つのコツ
仕事と学習を両立するコツとして、ここでは3つのポイントをご紹介します。
- ポイント①取得までのスケジュールを立てる
- ポイント②予備日を確保しながら、できるだけ毎日学習に取り組む
- ポイント③通勤時間などの隙間時間を活用する
スケジュール作成は両立の基盤です。例えば参考書を購入したら、「毎日20ページ前後読み、1ヶ月後に1周する」といった具体的な予定を立てましょう。この予定を立てないと、学習の開始そのものが遅れる可能性が高いです。
また学習は「週末に一気にやる」ではなく、毎日少しずつ積み重ねた方が学習リズムの定着に繋がります。ただし仕事の都合で予定通り進まない時も考えられるので、週に1回ほど進度を調整できる予備日を設けると良いでしょう。
Q. 働きながら資格を取るなら通信講座の方がいい?
難易度の高い試験に挑戦する場合や、学習への強制感を出したい場合は通信講座などの利用がおすすめです。ただし仕事の影響で「思ったように進められず、受講をやめる」といったケースも少なくありません。
そのため資格取得までのスケジュールや試験の難易度も考慮して決めましょう。
将来計画から資格を考えよう
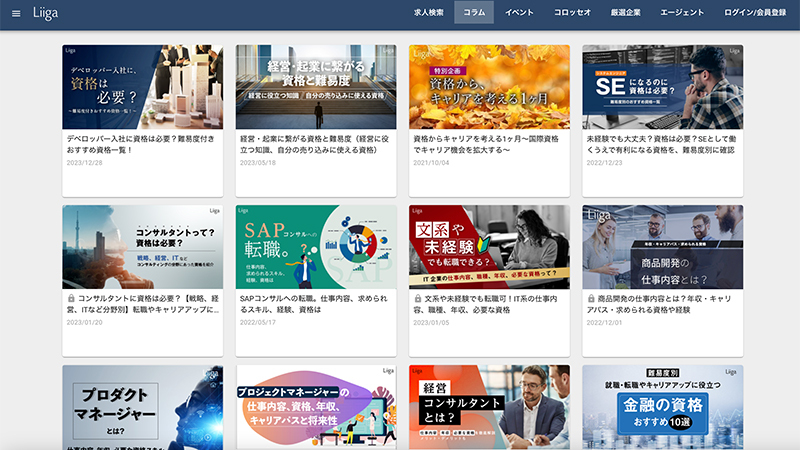
※Liigaの「資格」関係のコラム一覧画面(2024年2月21日時点)
資格取得の目的は人それぞれですが、働きながらの学習は楽でないからこそ、より自分の将来に活かせる資格を取得したいものです。そのためには、まず自分のキャリア計画やライフプランをしっかり考え、その方向性に合った資格取得を目指しましょう。
Liigaは転職者向けの総合ポータルサイトとして、求職者の方に役立つコラムを数多く掲載しています。各業界・職種におすすめの資格なども紹介しているので、参考にしてください。